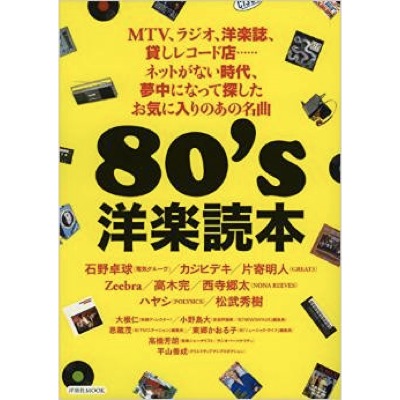『ジョン・ライドン 新自伝 怒りはエナジー』出版記念対談
日高央×小野島大が語る、ジョン・ライドンの比類なき音楽人生「ジョニーは革命を2回起こした!」

セックス・ピストルズの伝説的ボーカリストであり、同バンド脱退後はPiLを結成してポスト・パンク~ニューウェイブ時代を牽引したジョン・ライドンが、長大な自伝を上梓。2016年4月には日本語版『ジョン・ライドン 新自伝 怒りはエナジー』(シンコーミュージック)も刊行された。600ページを超える本書では、ロック史に残る毒舌家であるジョン・ライドンが幼少期から現在までの自身の人生を振り返るほか、セックス・ピストルズやPiLにおける楽曲制作の実際についても詳しく述べており、音楽家としてのジョン・ライドンの歩みをより深く知ることができる内容だ。今回リアルサウンドでは、同書の日本語版解説を執筆した音楽評論家の小野島大氏と、パンクロック全般に詳しい元BEAT CRUSADERS、現THE STARBEMSの日高央氏による特別対談を企画。ポピュラーミュージック史におけるジョン・ライドンの特異さ、偉大さについて、じっくりと語り合ってもらった。
どうでもいいエピソードも面白い(日高)
――セックス・ピストルズ/パブリック・イメージ・リミテッド(PiL)のジョン・ライドンの自伝『ジョン・ライドン 新自伝 怒りはエナジー』(シンコーミュージック)は、600ページにわたる大作です。マルコム・マクラレンとの確執などのピストルズ回りからPiLの音楽創作にまつわる話、2000年代のリアリティ・ショー出演の経緯まで、とにかく細かくエピソードが書かれています。
日高央(以下、日高):これは本人の語り下ろしですよね。あの短気なジョン・ライドンが、自分でこんなに長い文章をタイピングしたとは思えない(笑)。小野島さんは、本人に会ったことはありますか?
小野島大(以下、小野島):一度だけありますよ。かなり昔なんですけど、宝島で遠藤ミチロウさんとジョン・ライドンの対談があって、その司会を担当したんです。
日高:覚えてます! あれ、小野島さんの仕事だったんですね。
小野島:そうそう。PiLで来日した時だったんだけれど、その時の印象は、すごく愛想がいいというか、腰の低いサービス精神豊かな人、という感じで。1対1の単独取材だったらまた違ったのかもしれないけど、わりとイメージを作っているところもあるのかな、と思った。毒舌も含めて、ジョン・ライドンを演じている、というか。
日高:なるほど。パンクというものを背負っている感じはありましたね。演者の立場から言うと、メディアに出る時は確かに、何を期待されているか、みたいなことは常に考えちゃう。それが、ジョンの偉いところでもあるし、ハードコアに行きすぎないところかなと。シド・ヴィシャスだったら絶対そんなことやらないだろうし、いい意味でストイックすぎないというか、ちゃんとユーモアがありますよね。
小野島:普通に目立ちたがりだし、写真を撮れば勝手に中心のほうに行くし(笑)。そういう人ですよね。自伝もめちゃくちゃ饒舌で、そういうサービス精神が出ていると思う。
日高:ハッキリ言って、8割方はいらないエピソードですもんね(笑)。
――延々と友だちの話が続いたり。
日高:そうそう。周りに“ジョン”が何人いるとか、どうでもいいから早くシドを出せや!って(笑)。結局、シドが出てくるまでに300ページくらいかかるけれど、どうでもいいエピソードも可愛げがあるし、やっぱり面白くて。
小野島:語り口がいいよね。翻訳された方(田村亜紀氏)がうまいのかもしれないけれど、スルスルっと読んでいける。
――日高さんは、ジョン・ライドン、あるいはPiLについてどんな思い入れがありますか。
日高:世代的なところもあるんですけど、パンクロックはラフィンノーズからなんですよね。スターリンはデビューして、もうスゴいことになっていて、ラフィンがリアルタイムなんですよ。中1くらいだったかな。
小野島:それはメジャーデビュー前?
日高:そうです。全国ツアーで千葉木更津の「ヤンズ」っていうライブハウスに来るぞ、ということで、みんなで近所のダイエーに行って、迷彩のシャツとか買って(笑)。思い切りパンクっぽいってイメージするものを1000円くらいで揃えて、いわゆる“ダイエースプレー”で髪を固めたりして。結局、ラフィンはキャンセルになっちゃって、SYSTEMATIC DEATHとGASを観たんですけどね。そこからパンクが始まって、後追いでピストルズとかクラッシュを聴いていった感じですね。
その時、まずスピードが遅いなと思ったんです。今聴くと、ラフィンとかザ・ウィラードも遅いんですけどね。ただ、声がカッコいいし、ジャケットもカッコいいし、何よりルックスがよかった。ディグり甲斐があったし、リアルタイムじゃないけれどラッキーな世代ではありますよね。俺にとってジョン・ライドンのリアルタイムは『PiL LIVE IN TOKYO』(1985年)くらいからで、一番洗練されている時というか。で、PiLの音って、今でもすごいじゃないですか。
――確かに、特に初期アルバム3枚はすごいですよね。
日高:いま一緒にやっているドラムの高地(広明)は完全にAIR JAM世代で、当然、ラフィンもウィラードも知らないんです。それで、面白そうだと思ってPiLを聴かせてみたら、「これ、ヨガの曲ですか?」って(笑)。ジョン・ライドンはそういうことを言わせたくて、わざと「退屈だろ?」という曲を作る。その尖り具合がスゴいというか、日本のパンクスでそこまで突き詰めた人は本当に少ないと思います。
小野島:ミチロウさんはもしかしたら、ジョン・ライドンがPiLでやったことをソロでやりたかったのかしれない。
日高:そうですね。同時代だとソドムとか、ザ・ポップ・グループのようなことをやっていたり。ただ、当時は逆にソドムを先に聴いていたから、その二重構造が面白かったですね。日本のバンドを聴いて“かっけー!”と思って、ロンドンパンクの元ネタを探していくというか。そういう意味では、音楽オタクの元祖の世代でもあると思うんです。