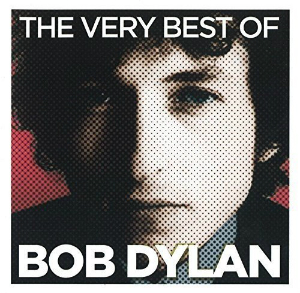『大人になって』インタビュー
odol ミゾベ&森山が語る、“美学とらしさ”「ポップスを一人ひとりのものとして捉えている」

東京を拠点に活動する6人組、odol。インディロック、シューゲイザー、オルタナティブ、ダンスミュージック、エレクトロニカ……といったジャンルで紹介するよりも「まだ見ぬ美しさを追求するバンド」と形容するほうが、彼らの音楽に対する紹介としては的確だろう。内面的な感性が結びついた音像と、思春期的な情景がたびたび描かれる歌詞の世界が、それを支える背骨になっている。
今年3月に「時間と距離と僕らの旅」を、そして5月に新曲「大人になって」を配信リリースした彼ら。通じ合うアーティストを招いた自主企画ライブ『odol LIVE 2018 "O/g"』のシリーズの開催も始めた。バンドに対する注目度も高まりつつある今、彼らは何を見据えているのか。すべての作詞を手がけるミゾベリョウ(Vo/Gt)と、作曲を担当している森山公稀(Pf/Syn)の2人に話を聞いた。(柴 那典)
「生活の中の全体的な美学を共有している」(森山公稀)

森山公稀(以下、森山):ありますね。ただ、『視線』以降で大きく変わったのは確かだと思うんですけど、それだけじゃなく毎回曲を作るたびに、バンドや音楽に対する考え方が変わってると思うんです。なので、そのタイミングで何かがあって大きく変わったというよりは、毎日積み重なってる。どんどん変わっている最中だと思います。
ミゾベリョウ(以下、ミゾベ):森山が言ったようにずっと変わっているとは思うんですけど、僕個人としては、2ndアルバムの『YEARS』を作った後に音楽への向き合い方がどうしたらいいかわからなくなって。そこで『視線』を作りながら悩んで答えを見つけていったというのはあります。
――odolって“これをやる”というような決まりごとや、こういうジャンルの音楽をやろうという枠組みもないと思うんです。それは自覚してやってるんですよね。
ミゾベ:そうですね。

森山:意識してやってるというよりは、もとから音楽を作る上で、どこかのジャンルやシーンに根付いて育ってないので。それによって何でもできるなというのもあれば、逆に損してるというのもあるんですけど。
――損をしてる?
森山:わかりにくいというか、普通にやっていたら説明しにくいバンドになってしまってるっていう。でも、無理してジャンルやシーンに根付いている風のやり方をやっても、それは本当ではないので。正直にやりたいことをやっていくっていうのを続けてる感じです。
――ミゾベさんはodolの音楽の自由度の高さについて、どんな風に捉えていますか?
ミゾベ:森山が最初にデモとして持ってくることが多いんですけど、僕も含めてメンバー全員がそれに「いいね」となるところから曲作りが始まっていくんです。自然とそうなるものって、今までやったことないこと、自分が見たことや聴いたことのない音楽が多いので。それに対して、たとえばこういうビートを乗っけたら他の人がやってないとか、こういうフレーズだったら聴いたことなくて面白いんじゃないかとか、そういう新しいことを探す作業で作っていくんです。「ジャンルにおさまらない」とよく言ってもらえるのは、そういう作り方だからなんだろうなって思います。
――ただ、ジャンルとか音楽性で括れないとはいえ、odolは「なんでもやる」というバンドではないと思うんです。だから、逆に「こういうことはやらない」というところにodolの美学があらわれているんじゃないかとも思っていて。そういうところって、みなさんとしてはどう捉えています?
森山:そういう美学の部分に関しては、音楽自体で「これはナシ」みたいなことを、あえて言葉で共有することは少ないです。どちらかというと生活というか、普通の会話の中で無意識のうちに共有されている感じですね。メンバーとも4年、ミゾベとはもう10年くらい一緒にいるので。生活の中の全体的な美学を共有していることで、バンドとしてまとまっていられるのかなって思います。同じシーンとかジャンルに属していなくても。
――“どう暮らしているか”とか、もっと広くて大きな価値観なんですね。
森山:そうですね。3年間活動してきて、インタビューで話したりするうちに“そういうことなのかな”って思ってきたところもあって。全体的な美学みたいなところを共有しようと頑張ったわけではないんですけど、そこが大事だったのかなって振り返って思います。

――僕が勝手にodolがやっていないことをキーワードで挙げるとするならば、“おふざけ”と“オラつき”かなって思うんです。“おふざけ”というのは、音楽で遊んだりユーモアのあることをやったりする感性。たとえば桑田佳祐さんや植木等さんとかがそうで。“オラつき”というのは、変な言い方ですけど、ライブのMCで「かかってこい!」って叫ぶような感性。odolはそういうことを言わなそうなイメージがあるんです。
森山:かかってこられたら負けますからね(笑)。でも、“おふざけ”に関しては思うところがあって。おふざけができるバンドは基本的に大好きなんですよ。YMO(イエロー・マジック・オーケストラ)だってお笑いと親密じゃないですか。