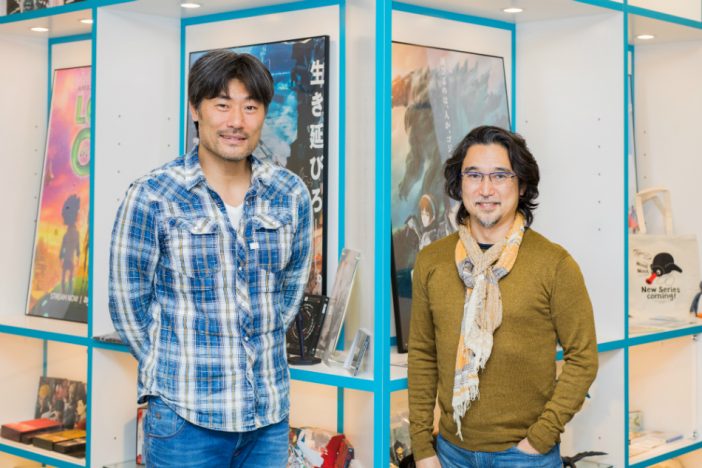世界に勝てるロボット開発のテーマは「妖怪」? ユカイ工学代表・青木俊介が追求する、ロジックに頼らないロボティクス

「ロボティクスで世の中をユカイにする」をテーマに、独自のロボットを次々と発表しているユカイ工学。チームラボの設立を経て、少年期以来の念願だったロボット制作に打ち込むべく同社を立ち上げた青木俊介氏は、「一家に一台ロボットがある世界」を目指し、人に寄り添う「妖怪のような」ロボットの開発を続けている。青木氏がロボットに魅せられた経緯から、世界的に話題になっているしっぽ付きのクッション型セラピーロボット『Qoobo』の開発秘話、そして今後の展望まで、じっくりと話を聞いた。(編集部)
「死屍累々」のロボティクスベンチャーに飛び込んだ理由
――青木さんがロボットに興味を持ったきっかけとして、『ガンダム』や『トランスフォーマー』のようなものではなく、“かわいいもの”が好きだった、というエピソードが印象的です。これは現在のユカイ工学のプロダクトにもつながる感覚ですね。
青木俊介(以下、青木):そうですね。ロボットが身近でかわいいもの、というコンセプトは、海外の展示では非常に少なく、「ベリー・ジャパニーズ!」と言われます(笑)。日本ではおそらく自然な考え方だと思いますし、僕自身が「こんな世界観がいいな」と憧れるのは、『となりのトトロ』だったりするんです。やはり「万能なロボットがひとつある」というのではなく、「身のまわりの見えるところにも見えないところにもいるんだよ」というのが面白いなと。「まっくろくろすけ」のようなものもいれば、トトロのように目立つものもいて。実際、IOTが行き届くとそういう世界観になるのでは、と思うんです。
――八百万の神々のような。そう考えると、「ネコバス」も自動運転のAIが搭載された車がこれくらいキュートだったら面白いですね。あらためて、ユカイ工学設立までの経緯から聞かせてください。
青木:大学時代、起業にはまったく興味がなかったのですが、インターネットが大好きで、プログラミングのアルバイトをしていました。90年代の終わりで、インターネットの出現で「スーパーマーケットも、国境すらもなくなる!」と、いまのAI以上に騒がれていましたね。インターネットで何かできたらいいな、というのは思いつつ、僕はやっぱりロボットがつくりたかったので、大学に残って研究者になるという道がいいんだろうな、と漠然と考えていて。
そんななかで、たまたま同じクラスになった猪子寿之くん(現チームラボ代表)が、ずっと「ベンチャー、ベンチャー」と言っていたんですよね。僕がアルバイトをしていたのもベンチャー企業でしたし、そのうちに「確かに面白そうだ」と思うようになって。とはいえ、仲間内で社会経験がある人間なんていなかったので、まずは手分けして、いろんな会社で働いてみよう、ということになったんです。僕はプログラミングのバイト、猪子くんはネット広告の会社で働いたりして、どうやってお金が回るのか、というところを探っていきました。そうして、4年生のおわりくらいに、チームラボを立ち上げたんです。親にはすごい反対されましたが(笑)。

――当初から、デジタルアートのようなものへの志向はあったのでしょうか?
青木:関心はすごくありましたね。ただ、最初は何かプロダクトをつくるということもあまり想像できませんでしたし、ホームページの制作やシステム構築を受託して、いろいろな会社の仕事をお手伝いしていました。アート活動のビジネスが大きくなったのは、起業からかなり経ってからだと思います。
――チームラボの立ち上げが2001年。青木さんは2007年にユカイ工学を立ち上げましたが、ロボディクスベンチャーを立ち上げようと決意したのは、どんな理由からでしょうか?
青木:ロボットへの関心はずっと持っていたのですが、ロボットは大企業がつくるものだ、というイメージがあったんです。SONYのAIBO(現aibo)だったり、HondaのASIMOだったり。そのなかで、愛知万博が開催された2005年あたりから、ベンチャー企業がロボットを出すというケースが少しずつ出始めて。アメリカでテクノロジー系DIYの専門雑誌『Make:』が創刊されて、それを読んだのも大きかったですね。それまで、ソフトウェアの世界では、無償で公開されたものがインターネット上で改良を加えられて、ビジネスの商用ソフトの性能を超えていく、という現象があり、そのおかげでさまざまなウェブサービスが生まれていましたが、それと同じようなことがハードウェア、デバイスの世界でも起こりつつあるんだと。そういう環境があったので、自分もトライしてみようと考えました。
――それまで世に出てきたロボットを見て、自分だったらこうするのに、と思うこともありましたか?
青木:そうですね。特にベンチャー企業のロボットは、みんなわりとメカメカしくて、ガンダムっぽいものが多かったんです。冒頭にもあったように、僕はそういうものよりぬいぐるみ、かわいいものが好きだったので、そういうロボットができないものかと考えていました。
――ユカイ工学のプロダクトは無機質さがなく、ユーザーとのコミュニケーションに比重があるように思います。そういうイメージは、当時から持っていたと。
青木:最初からありましたね。それで、2006年にチームラボを辞めました。ただ、これはいまもそうなのですが、ロボットをつくってそれがビジネスとして成功している会社はほとんどなく、まさに死屍累々という状況でした。
それでも起業しようと考えたのは、大学の先生にもいろいろとアドバイスをもらいにいくなかで、ロボットを研究でつくっている人はたくさんいても、ビジネスとして世の中に普及させようという人はほとんどいない、ということがわかったからです。研究の予算で数台つくって終わり、ではなくて、実際に世の中の人に使ってもらえるものをつくったほうがワクワクするし、これは意味のあることなのではと。
テーマは人のイマジネーションに寄り添う「妖怪」
――最初につくったのは、どんなロボットだったのでしょう?
青木:カッパのロボットでした。特徴としては、関節が柔らかくて、子どもが少し無茶な遊び方をしても壊れない、というところです。市販されているものは、握手なんかすると一瞬で壊れてしまう。ロボットなのに触れられない、というのは矛盾だと思いましたし、滑らかに動きながら、なでたり、抱っこしたり、あるいは枕投げのようにぶつけたりしても大丈夫なものをつくろうと考えたんです。
――つまり、これまでになかった「フィジカルなコミュニケーションがとれるロボット」をつくろうと。
青木:そうです。言葉によるコミュニケーションを志向すると、何百億円かけて開発したロボットでも、現状では「会話を楽しむ」というレベルにはまったく達していません。それは当然のことで、人間同士でも、知らない人と楽しく会話おするのって、かなりハードルが高いですよね。そうであれば、フィジカルなコミュニケーションで人を癒やす、という方が面白いのではないかと、当時から思っていました。カッパのロボットはプロダクトまではいけませんでしたが、「妖怪」をテーマにする、という発想は引き継がれています。
――「妖怪」と「ロボット」というのは、一聴するとかけ離れた存在のように思えますが、あらためてそのテーマについて教えてもらえますか。
青木:妖怪というのは、足音が後ろからヒタヒタと聴こえてくるとか、人間の五感を擬人化した、イマジネーションによる産物です。それが、ロボットと非常に近い。ロボットというのも、擬人化から生まれていますから。例えば、技術的なことだけを考えれば、自動改札機なんかは立派なロボットです。センサーがたくさんついていて、子どもはタダで通れて、大人が通ろうとするとブロックしますからね。でも、誰もそれに名前をつけたりしないし、ロボットだとも思わない。それはやはり、擬人化できないんです。それがルンバであれば、コードに引っかかっていたりすると、「がんばれ!」と応援したくなりませんか? そういうイマジネーションの働き方が、妖怪とロボットには共通しているんです。
また、ロボットがこれから進化を続けても、数十年という単位では、「ペット」を超えることはないと思います。犬や猫は、飼い主にとっては限りなく人間に近い。ロボットがそこまで到達するのは現状では無理なので、ペットほど近くはないけれど、でも人間のまわりにいる。それも、妖怪と似ているのではないかと。