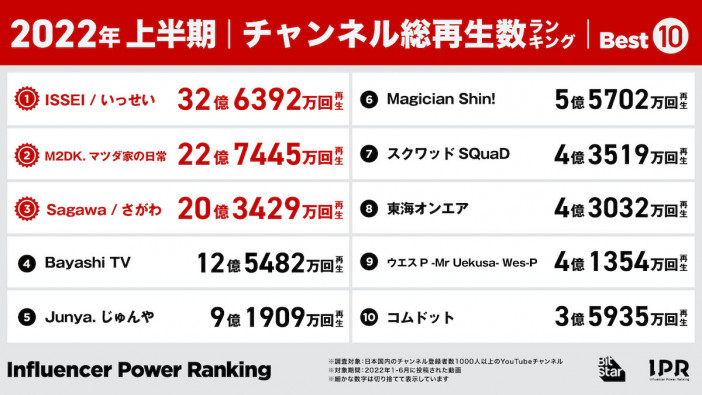「YouTubeを頑張るとCDが売れなくなる」という誤解を解いた先に YouTube音楽チーム担当者と考える“日本の音楽シーン”
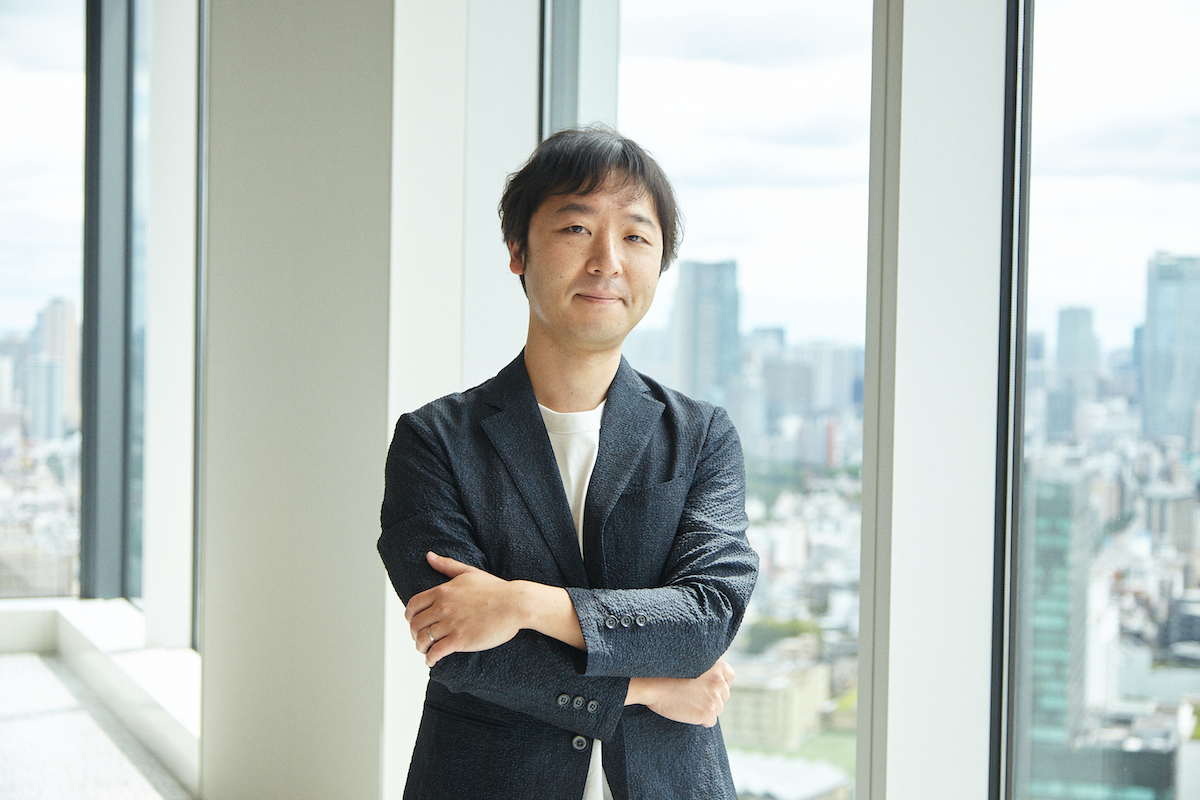
日本に上陸して15年、YouTubeが日本の音楽産業に与えた影響力は計り知れない。数多くのデジタルヒット創出の原動力となっただけでなく、ストリーミング時代のアーティストが国内外のファンと繋がり、音楽と映像を駆使する新世代の音楽クリエイターが個性を最大化する場所を提供してきた。YouTubeは今やアーティスト、音楽ファンやユーザー、そして音楽ビジネスと、あらゆる音楽領域で中心的存在にあると言える。そのYouTubeは、今の日本の音楽シーンをどう捉えているのか。そして、どこに向かおうとしているのか。
今回は、YouTubeで音楽チームを担当する、グーグル合同会社 日本音楽パートナーシップ統括の鬼頭武也氏に、日本上陸15周年を機に、日本の音楽シーンにおけるYouTubeの変遷と、今後の可能性について聞いた。(ジェイ・コウガミ)
「YouTubeを頑張るとCDが売れなくなる」と思われていた
ーーはじめに鬼頭さんが今、どんな仕事を担当されているか、教えて頂けますか?
鬼頭武也(以下、鬼頭):YouTube の音楽チームの日本統括をしています。音楽チームの構成を説明しますと、アーティストと向き合うアーティストリレーションチーム、レーベルと向き合うレーベルリレーションチーム、著作権やライセンスを担当するビジネスディベロップメントチーム、この 3つが柱になっています。私はGoogle Play Music立ち上げのタイミングでチームに参加しまして、現在は全体統括の仕事を担当しています。
ーーYouTube Japan15周年を振り返る意味で、日本の音楽業界は今までYouTubeをどのように捉えてきたのでしょうか? これまでを振り返って、業界内にはどんな意識の変化がありましたか?
鬼頭:私がYouTubeで仕事を始めた2015年、2016年は、 音楽業界にとってYouTubeは、公式コンテンツのプロモーションの場という認識でした。当時はまだ、多くのMVはフル尺ではなく、ショートバージョンで公開されていました。また、CD販促用のMVが主流で、15 秒や30秒の映像の後に「Now on sale」の文字が出るダイジェスト版でした。今のように、UGCクリエイターさんのカバー動画やコラボレーションもほとんどなかったです。当時は「YouTubeを頑張るとCDが売れなくなる」「音楽ストリーミングサービスの再生数とカニバるかもしれない」などを懸念する声も聞かれました。プロモーション用プラットフォームというYouTubeの見え方をどう変えていくか、ということが当時の私たちのアジェンダでした。
ーー当時、レーベル内にYouTube担当はいらっしゃいました?
鬼頭:いなかったですね。あるレーベルさんは、宣伝担当の方がYouTubeも担当されてたり。あるレーベルさんではデジタルビジネスの担当がYouTubeを見ていたり、とまちまちでした。
ーー日本の音楽業界がYouTubeを活用していこうというキッカケや転機は何だったと思われますか?
鬼頭:私が感じた一番初めの大きな転換点は、2016年から2017年に生まれたUGCコンテンツによるヒットの創出でした。たとえば、ピコ太郎さんの「PPAP」、星野源さんの「恋」です。ユーザーを巻き込んだ動画や、公式コンテンツ以外からヒットが生まれたことにより、音楽業界はYouTubeとUGCを絡めたヒット創出の可能性に気付いたと思っています。2個目の転換期は2018年にYouTube PremiumとYouTube Musicのサブスクリプションが始まったことです。2019年ごろにビジネス的な成果が出るようになり、ようやく業界がYouTubeをプロモーション目的から、収益化できるプラットフォームとして見始めました。この2つが転機でした。