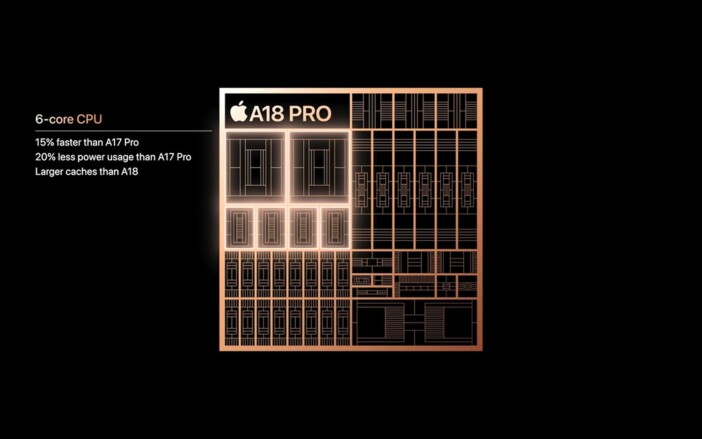“デジタル来世”は死を不平等にする? 話題のドラマ『アップロード』のテクノロジーから考える

人類は有史以来、死の恐怖と向き合い、これを克服しようとしてきた。
魂の存在や来世の存在を信じたりするのも、死という消滅の恐怖を緩和するためだったと言っていいかもしれない。誰しもに平等に訪れる死というものは、人類にとって永遠のテーマだ。
今日のデジタル技術の発展は、死の概念をも変えるかもしれない。自身の記憶や脳のデータを全てオンラインクラウドにアップロードして、肉体の死語もデジタル世界で生き続ける「デジタル来世」なる概念が登場したからだ。2020年5月からAmazon Prime Videoで独占配信されているオリジナルドラマ『アップロード ~デジタルなあの世へようこそ~』は、そんなデジタル来世が当たり前になった近未来を描いたSFコメディで、配信開始から1ヶ月を待たずしてシーズン2の製作も決定するほどの人気を博している。
本作は、将来デジタル技術によって命の定義が変わる可能性を示している。人生は死んだ後も続くとしたら、あなたはどのように振る舞うだろうか。シニカルなジョークが全体を包みながら、非常に深遠な問いを投げかける作品である。
自分の葬式に出席できる近未来
2033年、死が目前に迫った人々は、IT企業が提供する仮想現実に自分の記憶や人格をアップロードし永久に生きることが可能になっている。プログラマーのネイサンは自動運転の車が事故を起こし大怪我を負ってしまい、金持ちで我儘なガールフレンドのイングリッドに促されて、彼はホライゾン社が提供する最高級の死後の世界「レイクビュー」にアップロードされる。そこは24時間手厚い顧客サービスが提供される贅沢な空間。ネイサンは自分を担当するノラと出会い親密になってゆく。

この近未来では、様々な企業がデジタルで死後の世界を提供し、顧客獲得競争を繰り広げている。レイクビューはその中で最もラグジュアリーで、当然そのぶん料金も高額だ。支払う金額に応じて待遇も異なり、例えば、一番低額のプランでは、部屋は窓のない地下の殺風景な部屋で、月に2ギガバイトまでしか行動できないうえ、容量を使い切るとフリーズさせられてしまうのだ。
この世界では、VRを通じて現世の人々とも交流できる。自分の葬式に出席できるし、VR機能搭載のセックススーツを使えば、生きている人間とセックスすることすら可能だ。
ネイサンのアバターは、生身の肉体データから精巧に再現され、生きている頃と全く変わらない外見を手にしている。本作を観ているとネイサンが死んでいることを忘れてしまうほどに生前と同じ姿で行動し、思考する。本作の世界では、人は死を克服したかのように感じられる。
現実でもデジタル来世が実現する?
現実にも、デジタル来世実現に向けた動きは活発になっている。記憶の科学を研究するアメリカのベンチャー企業Nectcomeは、人間の脳を生きたまま取り出し、長期間冷凍保存するサービスを2024年以降に提供すると発表したそうだ。デジタル領域に脳の記憶をアップロード可能になるまで、脳を生きたまま保存可能だそうで、豚による実験では成功しているという。このサービス提供のためには、本人に肉体を捨ててもらう必要があり、実際に提供開始されれば倫理的な議論を呼ぶだろう(参照:いつかは永遠の命に? デジタル人格がもたらすもの)。

その他、マサチューセッツ工科大学メディア・ラボででは「Augmented Eternity(拡張される永遠)」というアプリの開発が進められている。これは死後、自分の代理としての人格をデジタルで作れるもので、脳そのものをアップロードする必要はなく、生前のライフログをAIの機械学習アルゴリズムに学習させて、その人物にふさわしい行動や発言をさせる。自分が今も生きているという感覚を得ることができるかわからないが、他者から見れば、その故人が今も生きているという印象になるだろう(参照:人類は永遠の夢「不死」をデジタルで手に入れるのか)。
死後ではなく、生前から自分のクローンをデジタル上に作る技術も研究されている。日本のオルツ社が研究する「P.A.I.(パーソナル人工知能)」は、人の膨大なデータをAIに学習させ、自分の意志をクラウド上に配置して、デジタル作業を肩代わりさせることを目的にしているという。日常生活のあらゆる情報をデータ化し、AIに学習させることで、自分ならこのように判断するだろうということを、デジタルの代理人格が自動的に処理してくれるようになるというのだ。これが実現すれば、日々の膨大なメールの返信などをデジタルクローンが代行し、自分自身はもっとクリエイティブな時間の使い方ができるようになるだろう。

オルツ社の「P.A.I.」は人間の「頭の中」を残すだけでなく、声や顔も残し、アバターを作成することも可能だそうだ。それらを後世に残していけば、デジタル来世とほぼ変わりないことが実現できる(参照:デジタルクローンが切り拓く未来【AI最前線 後編】BAE)。
死んだ人間とコミュニケーションが取りたいという願望は、主にその故人の親しい人や家族が抱くものだろうが、これを有名人や歴史上の人物に適用させることは可能だろうか。オルツ社のCFO・中野誠二氏は、「歴史上の偉人との対話は不可能」だという。なぜなら、どれだけクローンの精度が向上しても、過去の人物についてはAIが学習するデータが少なすぎるからだ。写真や映像データがあれば、アバターくらいは作成できるかもしれないが、その人物らしく自律的に振る舞うことは難しいだろう。
昨年の紅白歌合戦に登場した「AI美空ひばり」に対し「死者の冒涜なのではないか」という議論が起こったが、あれが再現しているのは声と外見だけだ。もし、より精緻なライフログが残っていて、AIに学習させることができたなら、AI美空ひばりは人々にどんな印象を与えたのだろうか。