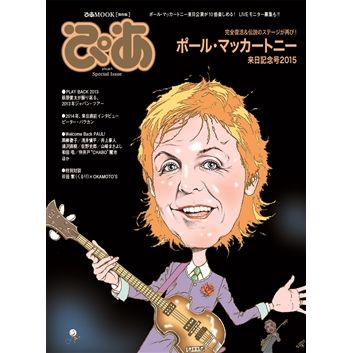市川哲史の「すべての音楽はリスナーのもの」第33回
ジェフ・リンの武器は〈世界一の無垢さ〉だーー市川哲史がELO14年ぶりの新作を機に再分析
インターネットの多大なる恩恵に与っている若い連中が、心の底から羨ましい。
冒頭からおっさん全開で申し訳ないが、検索すれば古今東西どんなロック/ポップミュージックでも「ひとまず」聴けちゃう、「下手すりゃ」動画まで視られちゃうのだから、なんと幸せなことか。あ、違法行為はやめようね♡(←棒読み)。
私なんぞは70年代中後期が中高生時代なだけに、まずレコードを買う資金力が乏しい。しかも地方在住だから安価の輸入盤店もないし、当時はまだレンタルレコード店は存在すらしていない。そもそも洋楽好きは少数民族だから、レコードの貸し借りにすら事欠く始末だ。いくらFMでニューアルバム丸々エアチェックし放題だったとはいえ、旧譜名盤から新作まで、全方位的にロックのカタログを聴くなんて物理的に不可能だった。
すると当然、聴くべきアーティストに優先順位がもれなく付くわけだ。英国産優先で米国産は後回しとか、ヒットチャート物はラジオで聴くだけか後輩に「買わせる」とか、どのアーティストも基本的にまずライヴ盤優先とか、いろんな不文律で自らを戒めてた気がする。
また、資料性に著しく欠ける当時の音専誌やLPのライナーを参照していろんなアーティストのディスコグラフィーを自作することで、あたかも聴いたかのような気分に浸ってみたり――ああ、涙ぐましいぞあの頃の私たち。
だから優先順位をクリアしてとりあえず一回りするのに、『ロッキング・オン』に書きながらの大学・社会人時代通して、最低10年は懸かったはずだ。あ、それでも足りなかったか。それでも天文学的なアイテム数にもおよぶ旧譜CD化バブルに、音楽評論家として立ち会えたことで、過去のロックの空白部を漸次埋められたのは幸運だった、とつくづく思う。
なのでエレクトリック・ライト・オーケストラを〈ちゃんと聴いた〉のも、1990年にまとめて初CDリイシューされた機会になってしまう。たぶん。
デビューアルバムの衝撃の邦題『踊るヴァイオリン群とエレクトリック・ロックそしてヴォーカルは如何に(THE ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA)』が示すように、当初は〈安直なオーケストラとの共演ではなくバンド内に弦&管楽器担当メンバーを配することで、クラシック的なサウンドと当時の最先端だったロックの融合〉がコンセプトの、多人数プログレ・バンドのはずだった。
ところがいざ「ロックとハーモニーとストリングスの合体(ジェフ・リン談)」を実践してみたらば、「エリナー・リグビー」やら「アイ・アム・ザ・ウォルラス」やら『サージャント・ペパーズ~』やらぽかったりと、その実験的だけど確信的でポップなサウンドは、言うまでもなくビートルズを思い起こさせた。その傾向は作品を重ねる毎に強まり、ELOのキャッチーで豪勢なニュー・オールディーズ・ポップソング群が、70年代半ばには全米チャートを圧倒するに至った。
そのストリングスによるキラキラしたサウンドが、『サタデー・ナイト・フィーバー』的なディスコ・ブームに似合ってたし、ELOのエンブレム的存在のジュークボックスの電飾を模したUFOが、『未知との遭遇』や『スター・ウォーズ』人気が沸騰したSF映画ブームにも合致したといえる。
なのでアルバムなら『オーロラの救世主』『アウト・オブ・ザ・ブルー』『ディスカバリー』、シングルなら「見果てぬ夢」「イーヴィル・ウーマン」「テレフォン・ライン」「ターン・トゥ・ストーン」「スウィート・トーキング・ウーマン」「ドント・ブリング・ミー・ダウン」「ザナドゥ」と、代表作をざっと挙げるだけでもキリがない。70年代当時地球上のどこかで棲息していた者なら、誰でも一度は聴いたことがあるはずだ。事実、〈70年代に最も全米トップ40ヒット曲を量産したバンド〉のギネス記録を保持している。14曲だったかしらん。全世界で5000万枚ものアルバムも売ったらしい。
よしんばELOを知らずとも90年代後期なら、奥田民生が好き者の本領を発揮したPuffyの「アジアの純真」を聴いて、知らぬ間にELOサウンドを疑似体験していたはずだ。また00年代には日本で「トワイライト」が、月面兎兵器ミーナが翔びまわる2005年放映のドラマ版『電車男』のOPを飾る主題歌として、24年ぶりに再ヒット。そして放送終了後もなお、ニュースやバラエティ番組ではまるでオタクや秋葉原のテーマソングかのごとく、最近まで流され続けていたし。
おそるべし〈ELOサブリミナル〉。
それほど、ほっときゃラジオから勝手に流れてきてくれたわけで、当時の貧乏高校生がELOを後回しにしたって責められないだろう。だってとにかく聴かなきゃいけないロックが、他にいっぱいあったんだもの。
しかし落ち着いて聴く余裕がようやく生まれたら、ELOはとにかく強烈だった。
「ELOを聴いたとき思ったよ、『サージェント・ペパーズ』に似てるって。あのチェロにバイオリン――僕らがビートルズでハマった力強いリフのストリングスだね。だから第一印象は『僕はオリジナルを知ってるぞ』。でも無視できない傑作だからね、僕らも先にやってりゃよかったと思ったさ(愉笑)。ストリングスはバッチリ、ヴォーカルも最高、ギターだって抜群だ。やっぱり僕はヒット曲が好きな性分なんだよ。だからELOは格別だな。皆と同じ音楽を聴くのは、たしかにダサいかもしれない。でも実際にいい曲なんだから、しかたない」
とのポール・マッカートニーの言葉を待つまでもなく、ヒット曲は問答無用で素晴らしい。そしてELOの楽曲は、〈ロック界の大林宣彦〉ジェフ・リンの脳内空間で鳴る〈ビートルズとそのルーツである1940~50年代の米国ポップス/ロックンロール/映画音楽〉たちが、リリース当時の流行音楽を「やや」先行するアプローチで解釈されてたからこそ新しかったし、見事に大ヒットした。
ちょっとだけ音楽評論家っぽく書けば、(1)アコギのカッティング、(2)多重録音で太くしたドラムのグルーヴ、(3)ストリングスもしくはシンセのエコーを効かせたリフ、によるジェフ・リン版ウォール・オブ・サウンドのキラキラ感もまた、魅力的だったのだ。安直なシンセ依存型キラキラとは、モノが違うのである。
いくら再評価しても再評価し足りない――と思っていたのはどうやら英国も同様なようで、昨年2014年9月、BBC RADIO 2主催の《Festival In A Day》に、13年ぶりに復活したELOがヘッドライナーとして出演すると、会場のハイド・パークは5万人もの大観衆で埋め尽くされていたのだ。先日リリースされたばかりのBD/DVD『ジェフ・リンズELO ライヴ・イン・ハイド・パーク2014』にその模様が収録されてるのだけれど、世代を超えた5万人が全曲盛り上がりまくる様子に、なんだかとても嬉しくなってしまった。