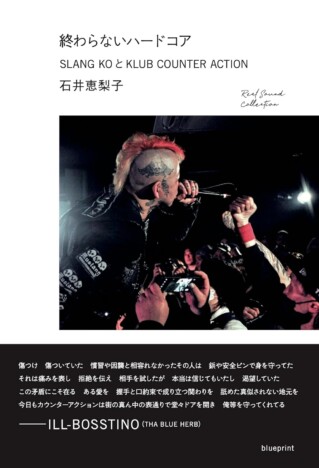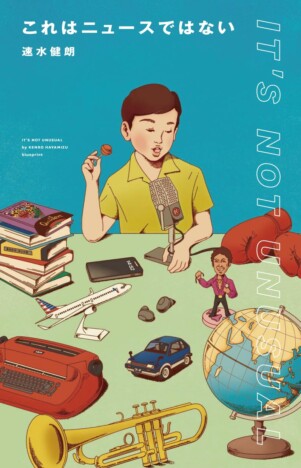『おむすび』制作陣は東日本大震災とどう向き合ったのか “母”になった橋本環奈の変化も

NHK連続テレビ小説『おむすび』が現在放送中。平成元年生まれの主人公・米田結(橋本環奈)が、どんなときでも自分らしさを大切にする“ギャル魂”を胸に、栄養士として人の心と未来を結んでいく“平成青春グラフィティ”。
妊娠・出産、東日本大震災の発生、さらには管理栄養士を目指す決意など、結にとって重要な出来事が重なり合った第15週。
制作統括の真鍋斎は「“病院で管理栄養士に出会って、管理栄養士を目指すこと”と“東日本大震災を描くこと”は最初から決まっていました。震災をどう位置づけようかと考えたときに、やはり主人公の成長譚としては“東日本に対して、つまりは社会に対して何ができるか”を考えるきっかけにしたいなと。震災を利用するわけではなく、“人間の力でどうしようもないところを、諦めずに人間の力で一歩でも良くしていくためには何をすればいいか”を彼女が考えるきっかけにしたい、というテーマがありました」と語る。

東日本大震災発生に伴い、ヒロインが被災地へ足を運び、被災者との触れ合いを描く。それこそがドラマのセオリーとも思えるが、『おむすび』では佳純(平祐奈)が現地の様子を伝えるという方法が取られた。
この展開について、真鍋は「まずひとつ、このドラマが日常的な事柄を描いている中で、果たして現地に行くことが正解なんだろうかと。従来の朝ドラのように、ヒロインがアクティブに何かを切り拓いていくのも痛快ですが、日常ってそういうことでもない気がするなと疑問がありまして。その中で、ヒロイン以外の登場人物たちが彼女に影響を与えていく、という作り方もあるんじゃないかなと考えました。子どもがいるから現地には行けないですし、そこは自然な流れでもあったと思います」と説明する。
同じく制作統括の宇佐川隆史も「『おむすび』ではそれぞれの登場人物を丁寧に表現してきたので、“避難所の食”についてしっかりと描きたいと思ったときにも、今までに出てきた人物の中に、ふさわしい人物がいると思っていました」と続けた。

被災地で直接的に人助けができなくても、管理栄養士になることで、より多くの人たちを救うことができる。結は「困っとう人がおったらすぐに助けるの、ずっと米田家の呪いやと思っとった。でも、呪いやない。これがうちのやりたいこと。うちの生きる道」と覚悟を決めるが、真鍋は「脚本の根本(ノンジ)さんと話していたのは、米田家の呪いとはつまり“惻隠の情”なんですよね。だけど、そのまま伝えても響かないのかなとか、正面から『素晴らしいでしょ?』というのは現代ではちょっと違うな、といったところで、あえて“呪い”だとしてきたわけです。呪いという言葉を使ってきたのは、ある種、我々の照れのようなものですね(笑)」と思いを明かした。
なお、“管理栄養士を目指す=栄養士からのステップアップ”という描き方について、「栄養士と管理栄養士は混同されてしまうこともありますが、明確に違いがあります」と真鍋。
「どちらも国家資格ではありますが、栄養士資格は栄養士養成施設(大学、短大、専門学校)で必要な単位を取得し、卒業すれば取ることができます。一方、管理栄養士資格は国家試験に受からなければ取得できません。ドラマの舞台になっている2012年当時の合格率は50%に達していないので、2人に1人が落ちる難しい試験なんですよね。今では4年制の大学を出て、国家試験を受けて管理栄養士になるパターンが多いですが、当時はまだその流れが確立されていなかった。法的には、栄養士の免許を取って3年間の実務経験を経て、試験に合格できれば管理栄養士になれるので、結にとってはステップアップだと思っています」(真鍋)