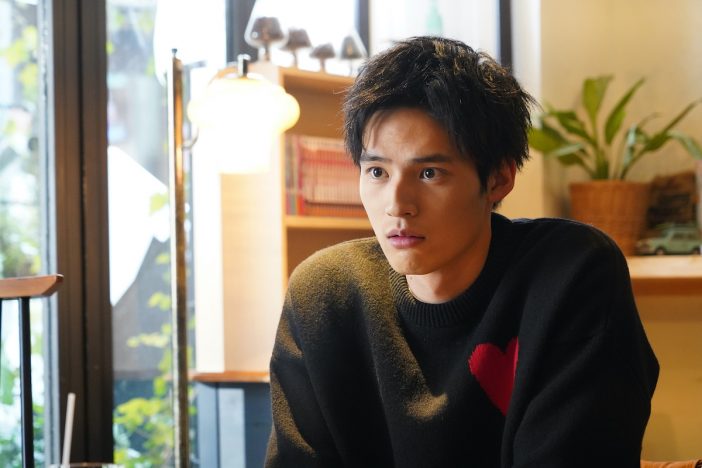戦後日本のテレビドラマ史は橋田壽賀子さんと共にあった 最後まで持ち続けた圧倒的な大衆性
2017年に出版された新書『安楽死で死なせて下さい』(文春新書)は、晩年の橋田壽賀子の心境が綴られた貴重な資料である。
タイトルのとおり本書には、安楽死をめぐる彼女の意見と、その裏返しとして強く主張される家族に依存しない人間観が、時にギョッとするような冷たい口調で書かれており、ドラマから透けてみえる橋田壽賀子の達観した家族観が、はっきりと伝わってくる。
本書の中で橋田は、山田太一や倉本聰を名脚本家、向田邦子に対しては天才脚本家で「妬みさえ湧いてきません」と書き、作家としての自分は二流だと語っている。
「高尚な芸術作品が一流のドラマなら、私の書くドラマはどれも二流です。ドラマが二流なら、書く人間も二流。私は二流人生で、一流になりたいなんて夢にも思ったことがありません。だって一流になったら、しんどいでしょう。その分、二流は気が楽です」橋田壽賀子『安楽死で死なせて下さい』(文藝春秋)より
テレビドラマ評論の歴史を遡ると、最も高く評価されてきたのは山田太一や向田邦子といった芸術的、文学的と称されるような脚本家の作品である。対して橋田壽賀子のドラマは、社会現象や物語性が語られることはあっても、ドラマ脚本家としては最後まで高く評価されることはなかった。それは彼女の脚本が説明過多で、全てを言葉で説明するものだったからだ。特に『渡鬼』は長セリフが多く、映像作品として見どころがある作品とは言い難い。同書の中で橋田は、1日中、忙しい主婦が画面に集中しなくても内容がわかるように、ラジオドラマのように「すべてをセリフで説明する」と語っているが、このような橋田のスタイルはテレビドラマの悪い部分として語られることが多い。
映画と比べてテレビドラマは映像表現として未熟。思っていることを全部セリフで説明するからダメだ。おそらく橋田壽賀子は、このような批判を何度も浴びてきたのだろう。この批判は映像論として圧倒的に正しいのだが、しかし一方で、セリフで全てを説明してきた橋田ドラマこそが、最も高い支持を受けてきたことは確かな事実である。
何より彼女は、自身が想定する視聴者である主婦の気持ちや立場を第一に考えて書き続けてきた。その目線は誠実で尊いもので、今の作り手に欠けていることだ。
本書の中にあるドラマ脚本に対する言及を読んでいると“私はこれでいいのだ”という迷いのなさを感じる。
おそらく、映像作品として文学性、芸術性を兼ね備えた高尚なテレビドラマは今後も作られ続けるだろう。しかし、橋田壽賀子のような視聴者に熱烈に支持されるドラマ脚本家はもう現れないと思う。テレビドラマは映像表現としての豊かさと引き換えに、圧倒的な大衆性を失ってしまった。橋田壽賀子だけが、それを最後まで持ち続けたのだ。
※記事初出時、一部記述に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。
■成馬零一
76年生まれ。ライター、ドラマ評論家。ドラマ評を中心に雑誌、ウェブ等で幅広く執筆。単著に『TVドラマは、ジャニーズものだけ見ろ!』(宝島社新書)、『キャラクタードラマの誕生:テレビドラマを更新する6人の脚本家』(河出書房新社)がある。