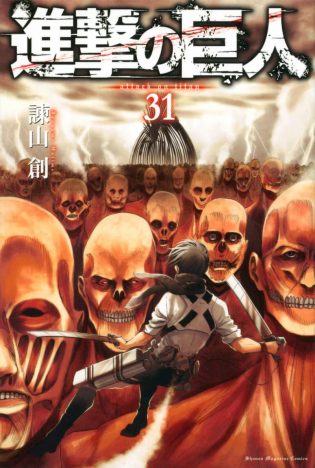『進撃の巨人』は時代とシンクロした作品だったーー評論家3名が徹底考察【前編】

倉田:杉本さんの話を受けて思ったんですけど、マーレ編以前の『進撃の巨人』は、ファンタジー・神話としての作品だったと思うんです。それがマーレ編になって、歴史・ドキュメンタリー要素の強い作品になった。世界の謎を解くというファンタジーだったものが、マーレ編以降、その世界の現実をどう生きるかという話になって、すごくリアリティーが増した。
渡邉:非常にいい喩えですね。というのも、特に『進撃の巨人』は物語初期の頃、「新しいセカイ系」みたいに批評・評価されていたふしがあったと思うんですよ。セカイ系のように、巨人が跋扈する世界の背景や歴史が一切描かれず、謎として提示される。でも後半、特にマーレ編の前後あたりから、完全に物語が転調して、この話の背景や歴史が明かされていく。セカイ系ではなくなっていくわけです。むしろ、まさに倉田さんがおっしゃったように、「社会」や「歴史」というセカイ系が描かないとされる中間項をドキュメンタリーのように描いていく方向に転調していった。
杉本:おっしゃる通りで、この作品が普遍的な世界の歴史を描いているのでは、という気になってきますね。色々な人が指摘していますが、マーレとエルディア人は、ナチスドイツとユダヤ人の関係を彷彿とさせますし、パラディ島編での戦いは、日本の幕末、開国派と鎖国派の戦いにも見えてきます。島の未来のためにいざ開国してみたら、さらなる地獄が待っているなんて、明治から昭和初期の日本みたいです。ただの空想ファンタジーではなく、人の歴史のドキュメンタリーが描かれているような感覚になります。
倉田:連載が始まった2009年頃に比べて、東日本大震災以降、どんどん現実世界がシビアになっていき、ある種の切迫感・緊張感みたいなものが熟成されていったのがここ10年くらいだと思っています。僕は諫山先生の考え方や世界の捉え方が、時代に合わせてアップデートしていったのが連載にも表れているんじゃないかなと思いますね。
渡邉:ここで私たちが言っていることに対して、どこまで諫山先生が自覚的なのかわからないですけどね。あと、後半は人類史の話になってくるじゃないですか。そうすると、これも2010年代後半に流行っていた、ユヴァル・ノア・ハラリの『サピエンス全史』とか『ホモ・デウス』を思い出す(笑)。やっぱりその時、その時のトレンドとシンクロしているのがよくわかります。それと同時にやはり作家としての諫山先生も、変化していったように思いますね。【後編に続く】