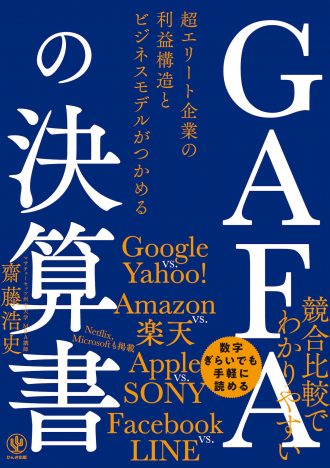ディズニープラスはなぜ事業として必要だったのか? CEOロバート・アイガーの半生に見る、ディズニーのイノベーション

読みどころ2:他のピクサー本と突き合わせて読むことで立体的に見える
アイガーは浮き沈みが激しく、人気商売であるテレビ業界の出身だ。これが今のように変化の激しい時代に組織をハンドリングするのにマッチしていたと言える。
彼はテレビマンとして駆け出しのころ、ABCスポーツを率いていたルーン・アーリッジから受けた影響をこう語っている。
ルーンから教わったことは、私のすべての仕事の指針になった。彼が残してくれた教訓は、イノベーションを起こさなければ死ぬということだ。そして、新しいものや証明されていないものを怖がっていたらイノベーションは起こせないことも、ルーンに教えてもらった。 ルーンはまた、完璧をとことん追求し続ける人だった。

ところが意外にも、ハリウッドにはこういう「イノベーションか、死か」という感覚の人物は少ないのだということがローレンス・レビー『PIXAR 〈ピクサー〉 世界一のアニメーション企業の今まで語られなかったお金の話』を読むとわかるのだ。
レビーは法律事務所勤務の弁護士を経てシリコンバレーのテック企業のCFO(最高財務責任者)を務めていたが、スティーブ・ジョブズに請われてピクサーに参画。1994年から2006年までCFOとして事業戦略策定などを担当した人物だ。
レビーの本にはこうある。
ハリウッドのイメージから、世の中のトレンドを先取りするクリエイティブで魅力的な世界を想像していたのに、現実は、ハイテク会社よりずっと現状維持に汲々としていた、変化を恐れていたのだ。どこに行っても、畏怖と力による政治ばかりに思える。映画会社は、アーティストも映画もテレビ番組も音楽も、なんでもとにかく支配下に置きたがる。
ハリウッドといえば創造性というくらいなのに、現実はまったく違う。これには驚いた。映画会社が大きなリスクを取ったりイノベーションを起こしたりするのは難しい。リスクを取るより、二匹目のドジョウで安全確実な道を選ぶのだ。つまり、エンターテイメント会社としてピクサーが身を立てるには、イノベーションを抑えるハリウッド流に染まらないようにしなければならないということだ。アットホームな文化を捨て、管理と名声の文化に染まれば、いま、ピクサーを支えているはつらつとした活力が失われてしまう。
アイガー以前のディズニーも例外ではなかった。それが証拠に、ピクサー側に立って書かれたレビー本ではディズニーはピクサーに不公平な契約を押しつけてきた難物(もっと言うと「悪の帝国」感すらある)として描写されており、ジョブズはディズニー側の振る舞いにしょっちゅうキレている。
ディズニーとピクサーのパワーバランスが変わったのは、もちろんピクサーが95年に作った映画『トイストーリー』以降、常識外れの大ヒットを一度のみならず生み出したからだ。
しかし両者が接近して2006年に買収にまで至ったのは、ディズニーのCEOがアイガーに替わり、ジョブズとの関係が改善されたからだったことが、アイガー本を読むと見えてくる。
ジョブズはアイガーの前のCEOであるマイケル・アイズナーと、とにかく折り合いが悪かった。アイズナーはアイズナーで1984年にCEOに就任して以降、ウォルト・ディズニー亡き後のディズニーカンパニーを再建し、テーマパークやリゾート事業を中心に大成長させた傑物なのだが(なおアイズナーにも『ディズニー・ドリームの発想』という著作がある)、レビーが懸念するようなタイプのハリウッドのやり手だった。
アイガー本によると、アイズナーはクリエイティブ以外の決定をほぼすべて本社の戦略企画部が下すように体制をつくり、この部署にいたのは、一流大学のMBAを持つ65人ほどのアナリストだったという。
そして、ディズニー側はすべての合意事項を重箱の隅をつつくように確認し分析してからでないと物事を進めなかったために、ジョブズはイラついていたのだ。
だからアイガーはジョブズに「これまでのような仕事の進め方はしない」「私に決断の権限がある」「ピクサーと共に未来を探っていきたいと熱望している」「それを素早く実行できる」と熱意を持って伝え、結果、買収交渉は成功した。
なおレビー本にもピクサーサイドから見たアイガーの印象が書いてあるが、アイガーが当時のディズニーのアニメ部門は深刻な状態にある(が、すべてのIP展開の大元にあるものとしてきわめて重要である)と認識していたからこそピクサーの才能が喉から手が出るほど欲しかったことはまでは書いていない。
こんなふうに、他のピクサー本やマーベル本などと突き合わせながら読むと、より裏側がよくわかる。そして制作現場以外にも資金面、経営面でも苦労があったんだなあと思いながら各作品を観ると、今まで以上に感動が増して見えてくる。
ディズニーブランドの安心感がありながらもイノベーティブでもある現在のディズニーが好きな人間は(あるいは嫌いな人も分析対象として)ぜひ読んでもらいたい一冊だ。
■飯田一史
取材・調査・執筆業。出版社にてカルチャー誌、小説の編集者を経て独立。コンテンツビジネスや出版産業、ネット文化、最近は児童書市場や読書推進施策に関心がある。著作に『マンガ雑誌は死んだ。で、どうなるの? マンガアプリ以降のマンガビジネス大転換時代』『ウェブ小説の衝撃』など。出版業界紙「新文化」にて「子どもの本が売れる理由 知られざるFACT」(https://www.shinbunka.co.jp/rensai/kodomonohonlog.htm)、小説誌「小説すばる」にウェブ小説時評「書を捨てよ、ウェブへ出よう」連載中。グロービスMBA。