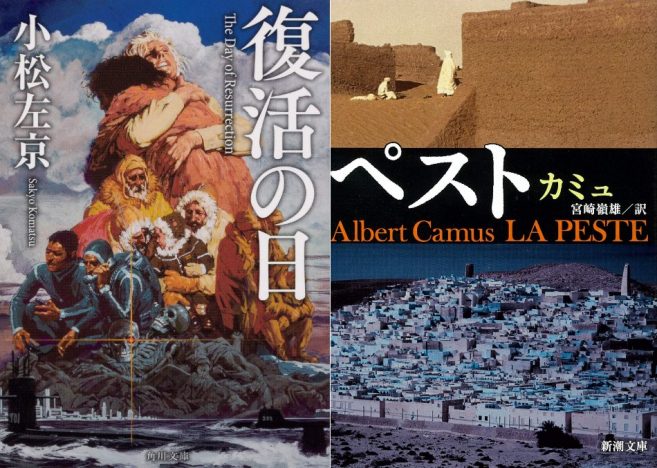『コロナの時代の僕ら』から考える、コロナ禍とミステリ小説の相似

ここには、死者をはじめ病気の被害者が存在する。ジョルダーノは自分たちを「自宅軟禁の刑に処された受刑者」に喩える。彼は新型ウイルス発生の背景に環境破壊があり「僕たちのせい」だと述べるが、それは「どうしても犯人の名を挙げろ」という声が世間にあることを意識したうえでの発言だ。また、誰から誰へウイルスが伝染したかしなかったかを探るのは、アリバイ調べのようなものだろう。犠牲者、犯人捜し、罪を問う声……。ミステリ小説にありがちなモチーフで、コロナ禍は語られているのだ。
感染症は「僕らのさまざまな関係を侵す病だ」とする著者は、関係の科学である数学の見方を使い、抽象化して状況をとらえようとした。こうした態度は、不可解な謎を論理的に推理して解き明かす、いわゆる本格ミステリの在り方に近い。このジャンルでは、真相の意外さを追求して無茶なトリックも考案されてきた。パズルのごとき遊戯として、人を人ではなく、体もただの部品のように扱って数として操作するような発想である。
そのなかでも、江戸川乱歩が考察したことでも知られるプロバビリティー(確率)の犯罪は、現状に通じるところがあると思う。乱歩は評論「プロバビリティーの犯罪」でそれをこう説明していた。
確率を計算するというほどではなくても、「こうすれば相手を殺しうるかもしれない。あるいは殺し得ないかもしれない。それはその時の運命にまかせる」という手段によって人を殺す話が、探偵小説にはしばしば描かれている。
ミステリとしては、だからその種の手段を用いて完全犯罪を企むというストーリーになる。一方、今の私たちは、自分が誰から病をもらうか、誰にうつすかわからない。気づかぬうちに自分が被害者に、加害者になりうるし、誰もが容疑者にみえて共犯者になりうる確率的可能性だらけの世界に生きている。私はミステリ評論も書いているため、そんなアナロジーからジョルダーノの数学的思考を理解していったのだった。
本書最後に日本語版のあとがきとして収録された「コロナウイルスが過ぎたあとも、僕が忘れたくないこと」は、特に強烈な印象を残す。書き出しは、こうだ。
コロナウイルスの「過ぎたあと」、そのうち復興が始まるだろう。だから僕らは、今からもう、よく考えておくべきだ。いったい何に元どおりになってほしくないのかを。
この言葉は、日本の人々に重く響くはずだ。コロナに関し緊急事態宣言が出されるすぐ前まで、この国は原発事故を伴った大震災からの復興を掲げた東京2020オリンピックの準備を進めていた。その復興は、元どおりになってほしくないことを含んでいなかったか。また、今回の危機が「過ぎたあと」、震災とコロナの二重の意味で復興しなければならないが、今度こそ元どおりになってほしくないことを忘れずにいられるのか。社会がよりよい選択をするためには、人間くさい私たちの行動を見つめつつ、抽象化して冷静に思考する必要があると本書は示唆している。
■円堂都司昭
文芸・音楽評論家。著書に『ディストピア・フィクション論』(作品社)、『意味も知らずにプログレを語るなかれ』(リットーミュージック)、『戦後サブカル年代記』(青土社)など。
■書籍情報
『コロナの時代の僕ら』
著者:パオロ・ジョルダーノ
翻訳:飯田亮介
出版社:株式会社 早川書房
https://www.hayakawa-online.co.jp/shopdetail/000000014512/