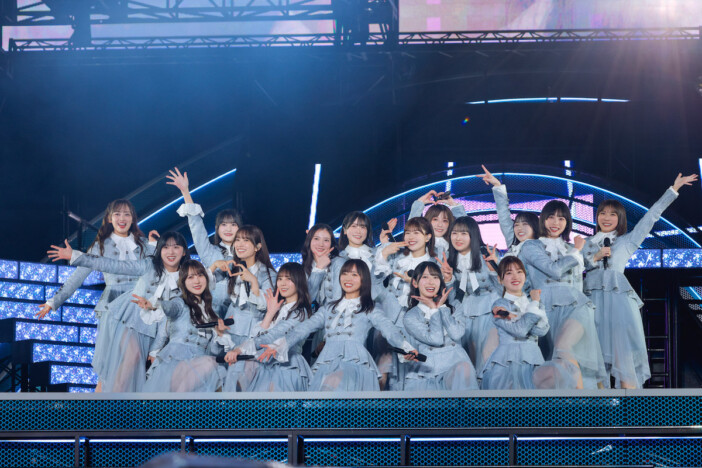Lucky Kilimanjaro、音楽×ダンス×雨が交差する歓喜の瞬間 日比谷野音に広がったドラマティックな光景

「Superfine Moring Routing」や「ON」、「ペペロンチーノ」、「エモめの夏」、「MOONLIGHT」など、『DAILY BOP』収録曲は、やはりその「動き」のある音楽や歌のもたらす躍動感が素晴らしく、曲間の熊木によるMCも、無理せず、肩ひじ張らず、隣からそっと語りかけてくるようなテンション感で、あくまでも自然体で音楽と繋がっているような感覚が心地よかった。きっとこの『DAILY BOP』を作ったことによって、彼にとって音楽はより「近い」ものになったのではないだろうか。もちろん、「SuperStar」や「Burning Friday Night」など2015年リリースの1stミニアルバム『FULLCOLOR』に収録された楽曲や、前作フルアルバム『!magination』に収録された「Drawing!」や「350ml Galaxy」、「とろける」、「春はもうすぐそこ」などの過去曲もたくさん披露されていく。

新曲と過去曲がバランスよく散りばめられながら、アンコールも含めて全25曲、予定調和的なカタルシスを演出するのではなく、延々とドラマチックな時間が続いていくような、そんな午前3時のダンスフロアでクラブミュージックを聴いているときのような高揚感が気持ちいい。時折、メンバーの姿が見えなくなるくらいにステージ上をすべて白い光で埋め尽くす、そんな強烈な色彩を放っていた照明も、ステージの上を照らすためというよりは心なしかステージから観客を照らそうとしているようにも見えた。
中でも私の頭にこびりついて離れないのは、すでに誰もが土砂降りの雨を受け入れ、そこに心地よさすら感じ始めている空気が会場全体に広がっていた頃に演奏された「夜とシンセサイザー」。この曲に関して、熊木は取材で「このコロナ禍における自分の葛藤が表現されている」と語っていた。その言葉を聞いていたからか、雨と照明とレインコートのフードで視界もおぼつかない中、あの重層的なシンセの音が鳴り響いたとき、その重みある多幸感に酔うと同時に、「どうやって生きればいい?」ーーこの曲の奥にある、そんな痛み混じりの叫びが聴こえてきたような気がしたのだ。

この雨はいつか上がるだろう。この音楽はいつか鳴り止むだろう。その先で、私たちはどうやって生きていこうか? きっとそれは、ラッキリの音楽の根底に常に存在する問いでもある。ピート・タウンゼントのあの有名な言葉のように、なんの解決も与えられないまま、迷いながら踊ることこそが音楽の醍醐味のひとつだろう。しかし音楽が止まったとき、私たちはどうすればいい? 生きていれば人は必ず決断を迫られる。なにを買う? どこに行く? 誰を選ぶ? 白と黒どっちにする?ーー踊り明かしたところで「問い」は消えてはくれず、私たちは常に選択を迫られ、「なにか」を、「どちらか」を、決断し続けていく。「なにも選ばない」ことは、用意された選択肢には含まれていない。
そんな日々を繰り返していく中で、私たちはときに、「失った」……そんな気持ちになるのだ。自分が選ばなかったものを想って。自分が選んだものの、隣にあったもののことを想って。そんな喪失感が付きまとう現実の残酷さを知るからこそ、私たちは忘れないようにしなければならないのだろう、迷いながら踊ったあの日のことを。答えは出ず、雨には濡れるしかなく、とても無力で、でもその無力さが平等で幸福だった、あの景色を。その記憶が、私たちの残酷な選択に、幾許かの優しさを与えてくれることを信じて。
雨が上がり、音楽が鳴り止み、新しい朝を迎える。毎日繰り返しのようで、実は同じものなんてひとつとしてない1日1日を生きていく。繰り返しているけど同じじゃない、というのはまるでダンスミュージックのようである。この新鮮で平凡な毎日に押し潰されそうになったとき、私は何度だって、あの日、土砂降りの春の雨の中で観たラッキリの姿を思い出す。
■天野史彬(あまのふみあき)
1987年生まれのライター。東京都在住。雑誌編集を経て、2012年よりフリーランスでの活動を開始。音楽関係の記事を中心に多方面で執筆中。Twitter(https://twitter.com/fumiaki_amano)