小説『モンパルナス1934~キャンティ前史~』エピソード2 マルセイユーカンヌ 村井邦彦・吉田俊宏 作

エピソード2
マルセイユーカンヌ ♯2
紫郎はマルセイユ・サン・シャルル駅の柱の陰で手洗いに行った富士子を待っていた。駅の外からアコーディオンの調べが聞こえてきて、耳なじみのある曲だと紫郎は思った。「サ・セ・パリ」だ。パリ行きの汽車の出発時刻が迫っているのに、富士子はまだ戻ってこない。もう10分以上も待っている。
「遅いな、富士子さん……」
と、その瞬間、紫郎は息をのんだ。改札の向こうに、小走りする富士子の後ろ姿がちらりと見えた。長い髪を後ろで結んでいる。その後を特高カラスがひたひたと追っていた。
「ふ、富士子さん!」
走り出そうとした紫郎を「パルドン、ムッシュー」と駅員が呼び止めた。
「悪い、急いでいるんだ」
駅員は強引に紫郎を押しとどめ、紙きれを手渡した。日本語の走り書きがある。
「ごめんなさい。追われているのは私です。説明している時間はありません。あなたはカンヌへ行って。どうかお気をつけて。フジコ」
紫郎は紙きれと動き出す汽車を交互に見ながら、しばらく息をするのも忘れていた。
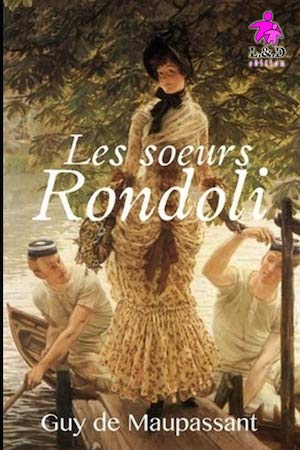
ジェノヴァ行きの列車がマルセイユを出発した。空いている席にどっかりと腰を下ろして、紫郎は大きくため息をついた。自分はすべてを打ち明けたのに、富士子はなぜ話してくれなかったのか。あのカラスのターゲットは自分ではなく、富士子だった。もう追ってはこない。紫郎はどこか安堵している自分に腹が立った。
紫郎を乗せた汽車は海岸沿いを東に向かってゆったりと走っている。延々と続く海岸にはゴツゴツした岩が露出して、穏やかな地中海の波に洗われていた。初夏の強い日差しを受けた波がキラキラと輝いている。
内陸に入ると小さな谷や丘の斜面のいたるところにツル薔薇の森が見えた。ツル薔薇は生垣や壁をはい上がり、屋根や樹木に広がって赤や白の花を咲かせている。バラの周りにはオレンジやレモンの木々が立ち並び、白い花を咲かせていた。早くも金色に輝く実をたわわにつけている木も見える。
紫郎は中学の頃に読んだモーパッサンの短編小説『ロンドリ姉妹』を思い出した。主人公は紫郎と同じようにマルセイユからジェノヴァ行きの汽車に乗ってコート・ダジュールの海岸線を走るのだ。モーパッサンはこう書いている。(※)
「まさに薔薇の楽園であり、オレンジやレモンの花咲く森だ」
「ここは香りの王国でもあり、花々の祖国でもある」
紫郎は愛読した本に描かれていた情景が、こうして実際に存在していることに胸を打たれた。今までこんなに豊かな自然は見たことがなかった。
「ああ、なんて美しいんだ」
紫郎は思わず小さくうなった。
汽車はいくつもの丘を上ったり下ったりして、海沿いの崖の上に出た。窓を少し開けると紺碧の海から潮の香りが入ってきた。日本でも経験のある匂いだが、時折、レモンの花の強烈な悩ましい甘い香りが混じって漂ってくる。
紫郎は富士子の長い髪を思い出した。彼女は髪を後ろに結んでパリ行きの列車に駆け込んだ。「気合を入れるときに結ぶ」と言っていたから、決意の末の行動だったに違いない。

「やあ、どうも」
紫郎の向かいに若い男が座って、にこりと笑った。プール事件の男だった。
「き、君はあのときの」
「なんだよ、幽霊を見たような顔をして」
プールでは紫郎より年下に見えたが、少し年上かもしれない。男は村上明と名乗り、明治大学を休学してイタリアで彫刻を勉強するのだと言った。
「あの背の高い美人と一緒じゃなかったのか」
「ああ、船で知り合って、ちょっと仲良くなっただけさ。そういえば、あの後、君からお礼を言われたって聞いたけど」
「えっ、お礼だって? 俺が? まさか、冗談だろ。君はあの女のことをどのくらい知っているんだ」
「パリに行って絵の勉強をするって聞いたけど……」
「俺はあの女を東京で見たことがあるんだ。明治の1年先輩に林田っていう官憲にマークされているマルキストがいるんだけど、彼と一緒に活動していた妹だ。間違いない」
紫郎は耳を疑って、しばらく沈黙した。
「なんだよ、何も聞いていなかったのか。まあ、話すわけがないか」
「彼女は森田って名乗ったんだが」
「そいつはいいや。林田のはずだ。木を1本植えたんだよ。君に気があるって意味かもな」
村上はクスクス笑って、話を続けた。
「あの女はちょくちょく三等の食堂に現れていたんだ。一等の食事は肩が凝るって誰かに話しているのが聞こえたから、それは本当だろう。一等は昼も夜もコース料理なんだろう? ボルドーのワインが1人に1本付くと聞いたぞ。ブルジョワだな。まあ、とにかくあの女は長身の美人だから目立つのさ。何度か見かけて、やっぱりあの林田の妹だって確信したよ。ヨーロッパ人みたいな大きな目が兄貴にそっくりなんだ。それで問題はそこからさ。遠くからじっと彼女を見ている男がいたんだよ。あの女が来るたびに、毎回、姿を現すんだぜ。怪しいだろう? にやけた妙な野郎だった」
「痩せぎすの30ぐらいの男じゃないか?」
「そうそう。なんだ、君は知っていたのか」
「いや、確信は持てなかったんだけど」
「俺は彼女に言ってやったんだよ。妙な男に尾けられているようだから、気をつけろってね。あの女は笑って相手にしなかったけど、どこか心当たりがありそうな顔をしていたな。林田の兄貴の方は特高に捕まったって噂に聞いた。あの痩せぎす野郎も特高だな。海外に逃げた妹を追ってきたんだ」
紫郎は髪をかきむしり、拳で自分の膝をゴンゴンとたたいた。思い出したように顔を上げ、村上の身なりを上から下までまじまじと眺めた。
「おいおい、なんだよ、男に見つめられてもうれしくはないぜ」
この男も特高ではないかと紫郎は疑ったが、確かめる方法はなかった。
「おい、川添君と言ったな。俺は第六感には自信があるんだけどさ、君も見張られているんじゃないか?」
村上の言葉が紫郎の急所にぐさりと刺さった。列車は何度かトンネルを抜け、いくつもの岬を越えながら、相変わらず美しい海岸沿いを走っていた。
「み、見張られているって?」
「ああ、そうさ。あとでゆっくり後ろを見てみろ。向こうの車両に高そうな背広を着て紺のネクタイを締めた40ぐらいの東洋人が座っている。いや35ぐらいかな。恐らく日本人だ。俺が君の前に座ったとき、一瞬だが驚いたような顔をした。ずっとこっちの様子をうかがっている気がする。フランスの新聞を広げているが、さっきからページをめくった形跡がない」
紫郎は村上の注意力と観察力に感心した。
「あの船の客だったのか」
「いや、見かけなかったな。マルセイユで待ち構えていたんじゃないか」
「まさか」
「そもそも君は官憲にマークされる覚えがあるのか?」
「い、いやあ、どうかなあ」
村上を完全に信用したわけではなかった。警戒するに越したことはない。
「まあ、いいさ。君は一等に乗るくらいだから、金持ちのボンボンなんだな。三等の船室はひどいもんだぜ。一等と三等じゃあ、扱いが全く違うからなあ。階級社会の縮図だよ、あの船は」
「僕もそう思ったよ。船内の階級だけじゃない。あんたも見ただろう。上海、香港、サイゴン、ボンベイ。どこも西洋の植民地になって、アジア人がこき使われている。白人の天下じゃないか」
紫郎は背広の男の視線を背中に感じながら、声を低くして言った。
「ああ、そうだな。しかし、今では我らが大日本帝国も西洋と同じことをやっているじゃないか。アジアを植民地にして……」
村上が急に口をつぐんだ。紫郎は目で「どうした?」と訊いた。
「背広野郎がにらみやがった。バチンと目が合った。あの眼光、ただ者じゃないぞ」
村上が下を向いて靴ひもを直すふりをしながら小声で言った。列車が速度を緩めている。フレジュス駅に到着したのだ。確かここには古代ローマ時代の闘技場があったはずだ。
「ちょっと試してみるか」
紫郎がそう言うと、村上は低い声で何をするつもりだと訊いた。
「心配するな。君に迷惑はかけない」
短い停車時間が終わる頃、紫郎はリュックを背負って窓からひらりと外に飛び出し、改札に向かって歩き始めた。もう列車は動き始めている。10秒ほど遅れてネクタイの男が列車から飛び出してきた。
「驚いたな。本当に出てきた。よし、見ていろ」
紫郎はさっと身をひるがえし、猛然と汽車を追い始めた。後ろを見るとネクタイ男も必死に走っている。
「韋駄天シローをなめるなよ」
早稲田高等学院時代は100メートルを11秒台で走った。サッカーでは5人抜きでゴールを奪い、野球で塁に出れば二盗、三盗は当たり前で、本盗を決めたこともある。汽車がホームを離れる寸前、紫郎の指がギリギリのタイミングで最後尾の車両の手すりにかかった。
けたたましい蒸気の音と高級背広の男を残し、紫郎を乗せたジェノヴァ行きの列車は颯爽と走り去った。




















