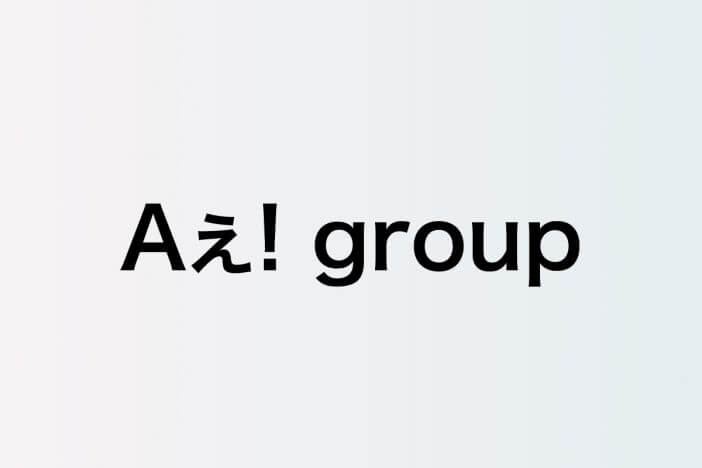堂本剛は時間も空間も超えた大きな流れの中で歌う 『東大寺LIVE 2018』映像から感じたこと
異なるカラーが混ざり合うグラデーションの中で、異なる意見を咀嚼する楽しむ余裕、お互いを許し合う柔軟さ、偶然的に生まれた何かを面白がるゆとり……そんな曖昧さを受け入れる心にこそ“愛”が宿るのではないだろうか。
〈愛を見失ってしまう時代だ〉。堂本は16年前に、ソロデビューシングル「街」で、すでにそう歌っている。「ジャニーズだから」「アイドルだから」とセパレートされたイメージばかりが独り歩きし、押しつぶされそうになった堂本の心を解放したのは音楽だった。だが、その音楽作品に対しても「アイドルの堂本剛が、本当に作ってるのか」などという冷ややかな反応が起こり、彼を傷つけてきた。
そんな堂本が愛してやまないのが、FUNKだ。『SONGS』では、MCの大泉洋にFUNKの魅力を伝えるべく、即興演奏を披露した。コーラスメンバーと〈Oh(大) Spring(泉) Yo(洋) Mo-jya Mo-jya(もじゃもじゃ)〉のみの歌詞を繰り返し、堂本の表情を見ながらバンドメンバーが心の赴くままに音を奏でる。気づけば会場には、FUNKとは何かとか、堂本が何者だとか、そんなことにとらわれる人は誰ひとりおらず、ただただそこに鳴り響く音に観客も大泉も体を揺らして酔いしれた。
「ゆるく、雑談しながら、良い意味で適当にやったほうが、カッコいいものが最終的にできあがる」。公開されたレコーディング風景を見ても、堂本の周りにはいつだって余白が作られていた。締切が迫る中でも、床に置かれたギターケースを見つけて、「座椅子みたい」「席外してる」などと仲間同士で笑い合うのだ。
生きていることそのものを、そして誰かと心を通わすことで鳴る音に身を委ねる。それが、堂本の奏でる音楽だ。『東大寺LIVE』のDVD&Blue-rayリリースを受けて、ラジオ『堂本剛とFashion & Music Book』で、堂本は「言葉では説明していないけれども、感じ取っていただけるものが、たくさんあるんじゃないかなと思うので、是非、じっくり、その空間にたたずんでもらえたらなというふうに思っております」と語った。
ただ、感じるままに音楽を味わう。それは、そのまま生きることと向き合う作業なのかもしれない。混ざったり、揺れたり、時には涙で言葉につまったり……音を感じようとする姿勢が、言葉以上に伝わることもある。現代社会に生きづらさを感じている人にこそ、セパレートせず、フラットな感覚で、堂本の鳴らす音に身を委ねてほしい。
(文=佐藤結衣)