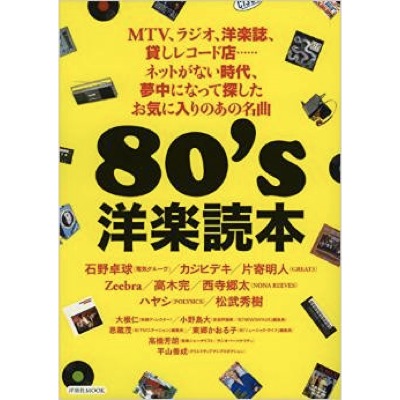『私たちが熱狂した 80年代ジャパニーズロック』執筆陣集合
【座談会】小野島大・中込智子・兵庫慎司が語る、80年代邦楽ロックのターニングポイント

「パンクや、インディーズの人間はメジャーを想定していなかった」(中込)
――中込さんには町田康さんのインタビューをお願いしましたが、80年代前半とともに、ちょうどいま話に出てきた85~86年がターニングポイントだということでしたね。
兵庫:BOØWYフリークの代表としてインタビューさせてもらった、ソニー・ミュージックアーティスツの道下(善之/現電気グルーヴマネージャー)さんもそうおっしゃっていました。やっぱり85、86年だって。
中込:その頃から、ライブハウスにも急に人が入るようになったんですよ。東京ロッカーズの頃――私が高2のとき、バイト先にミスター・カイトのベーシストの尾崎さんという方がいて、誘われて初めて渋谷屋根裏に行ったんですけど、当時は人が少なくて。カトラトゥラーナとかが対バンだったと思うんですが。
――東京ロッカーズって、後の世代から見ると華々しい印象がありますが、当時の現場は人が入ったり入らなかったりだったのでしょうか。
小野島:フリクションとリザードは集客力が高かったけど、それ以外は大したことなかった。「DRIVE TO 80's」(1979年)みたいな複数のバンドが一杯出るイベント形式のライヴはよく入ってましたね。
中込:流れとしては80年くらいにハードコアが始まって、それからGAUZEが自主企画「消毒GIG」をスタートさせて、徐々に人が増え始めて。パンクスも、それまでは原宿に行くとちょっと見るくらいだったのが、目に見えて増えていきましたね。で、85年にラフィンノーズが新宿アルタ前でソノシートを無料配布すると言ったときに、「ファン、こんなにいるの!?」みたいな。私ももらいに行ったんですけど、そこに集まった誰もが、人数に驚いていました(笑)。
――小野島さんは、「自主制作」と言っていた時代と「インディーズ」ができてからでは、質的な変化は感じましたか。
小野島:単純に流通網が整理されて、いろんなところでCDが手に入るようになったというのが大きかったですね。レコード制作のノウハウも完全に手探りだったのが、だんだんと憶えてきて、小さな産業として成り立つようになった。それが83~84年くらいかな。本にも書きましたが、そこからだんだん「自主制作」と言っていたものが「インディーズ」というお洒落な言葉になって。そうこうしているうちに、いつの間にかラフィン、ウィラード、有頂天の「インディーズ・ブーム」が来たという。その少し前の83年にAUTO-MODが「時の葬列」というシリーズ・ギグをやり始めてすごく盛り上がって、あれもブームに繋がるひとつの、きっかけでしょうね。AUTO-MODは、布袋寅泰と高橋まことがBOØWYと掛け持ちで参加していた時期があって。GENETに言わせると、最初の頃はどう考えてもAUTO-MODのほうが動員が多かったから、布袋もそこで知名度を上げたんじゃないか、みたいなことでしたけど。
中込:ただ、当時はもうBOØWYはメジャーデビューしていたんですよね。レコード会社が違っていて。
小野島:最初はビクターですね。黒っぽい服を着て、最初は「暴威」って、漢字表記だった。デビューした時はアルファベットになっていた。AUTO-MOD時代は布袋氏も楽しかったんじゃないですかね、AUTO-MODで、海外の最新の音楽を取り入れてガンガン弾いて。その実験の成果をBOØWYにまたフィードバックしていく。
――布袋さんのようにメジャーに行く人と、インディーズの交流というのは続いていたのでしょうか、それとも分かれていたのでしょうか。
中込:その頃は完全に分かれていて、メジャー組は、ビートロック系が中心でしたね。例えば、ザ・ストリート・スライダーズもいたし、あとはザ・モッズとか、九州のビート系の流れがあって。
小野島:ザ・ルースターズとザ・ロッカーズが出てきて、モッズは少し後。モッズはやっぱりレコード会社が強かったから、バッと売れた気がする。
兵庫:ライブハウスなりインディーズがメジャーの予備軍ではなかったんですよね。いきなり1枚目からメジャーでやるバンド、ずっと自主制作でやるバンド、って分かれてて。
中込:もともとパンクや、インディーズの人間はメジャーを想定していなかったし、いけるものとは誰も思っていなかったから、それでメジャー志向のバンドと分かれていたんです。“俺たちには関係ない”と。そんななかでパンクが売れてインディーズブームになって、有線なんかを上手に使い始めて。最初にかかったのは遠藤ミチロウの「仰げば尊し」やラフィンノーズの「ゲット・ザ・グローリー」で、普通にリクエストでかかるような時代になり、とても嬉しかったのを覚えていますね。
小野島:でも、この間、調べていてびっくりしたんですが、ザ・スターリンのメジャー1stアルバム『STOP JAP』(1982年)はオリコンで3位までいってたんですよね。あの手のアングラでハードなパンクとしては空前絶後の売れ方じゃないですか。
中込:スターリンの売れ方は特殊でしたよね。当時はパンク系を扱う音楽誌は1~2誌しかなかったなか、『アサヒグラフ』とか『フライデー』みたいな週刊誌に載って、社会現象的に知られるようになった。非常にショッキングなライブの様子がそうした週刊誌から衝撃をもって伝えられていった。
兵庫:僕はその頃広島の田舎にいたんですけど、それこそ『フライデー』とか『週刊文春』の情報しか入ってこなかったですから。ミチロウさんがステージで全裸になっている写真とかブタの臓物をぶちまけている写真が載ってて、過激だって書いてあるんだけど、田舎ではそうそうレコードが手に入らない。そんなときに、渋谷陽一が『サウンドストリート』(NHK-FM)でスターリンをかけて、それで初めて聴いたんです。すごいびっくりしたのを覚えていますね。83年頃かな。
小野島:スターリンは演奏するのが簡単だったんですよ。簡単にコピーできて、かっこいい。だから、みんな真似してバンドでコピーする。
中込:学祭などでもスターリンのコピーをやるバンド、かなり多かったですよね。
小野島:それって、ポップカルチャーが普及する条件じゃないですか。かっこよくて簡単に真似られる、俺でもできそうな気がする、と。
兵庫:BOØWYもレベッカもブルーハーツもそうだし、ラフィンもそうだ。たくさんコピーされていましたね。
中込: 83~84年でそうなって、85~86年でレコード会社から声がかかるようになって、バンドが次々デビュー、みたいな流れですね。みんなまだ20代前半の子どもだから、「どうやらお金がいっぱいもらえるらしい!」「給料がもらえるかも?」みたいに、夢が広がっている感じだったと思います。町蔵さんのINUとか、メジャーから出た名盤もたくさんあったけれど、85年以降の流れはそういうのとはまた違う感じだったかも。