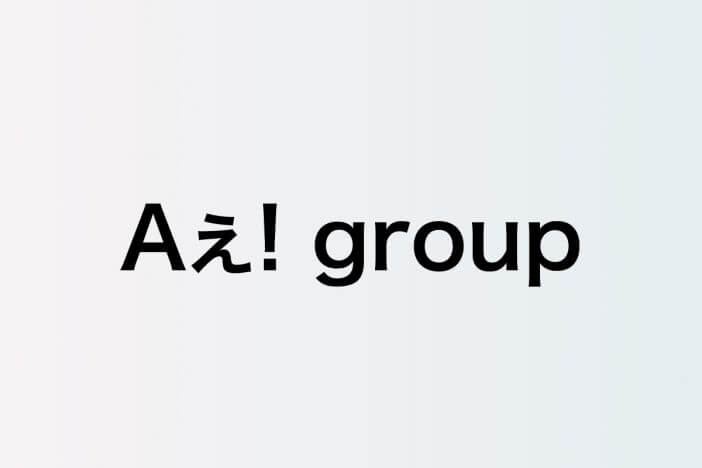メロキュア特集Part.3:佐々木敦がメロキュアの核を読み解く
メロキュアの新作に感じる“完璧な流れと繋がり” 佐々木敦が「復活」の意図を読み解く
たとえば私は先日、小西康陽のPIZZICATO ONE名義のアルバム『わたくしの二十世紀』を聴きながら、思わず陶然としてしまった。小西氏が過去に書いた曲の録り直しで構成されているのだが、どの曲を聴いていても、まさに最初から最後まで音符が全て綺麗に繋がっており、旋律が流麗に流れている。おかしなところ、気に障るところ、不具合な部分が、まったくないのである。ああすごいな流石だな、と私は思った。そして、こういう安心しつつも瞠目させられる音楽の、今や如何に少ないことか、と嘆息したのである。
さて、メロキュアの『メロディック・スーパー・ハード・キュア』を一聴して、私が最初に思ったのは、ここから聴こえてくるメロディも、完璧な流れと繋がりを持っている、ということだった。冒頭の「Pop Step Jump !」から最後まで、一曲たりとも、音を耳で辿りながら疑問符が生じたものはなかった。しっくりくる、という表現が近いだろうか。既聴感が発動しないわけではない。むしろ「1st Priority」や「「虹を見た」」など、Jポップがまだ歌謡曲と呼ばれていた時代にまで遡る様々な音楽的記憶が閃くのだが、それらがひと続きの曲として流れ出した時、紛れもない「メロキュアの曲」としての輝きを発するのである。これは是非とも強調しておきたいのだが、こういうことは本当に滅多にないことなのだ。私のベストソングは、ディスク2にクラムボンのミトとkz(livetune)による秀抜なリミックスも収録されている「Agapē」。普遍的な魅力を持った名曲だと思う。もちろん他の曲にも、タイムレスなメロディラインが詰まっている。こんなことが、どのようにして可能なのかは私にはわからない。だがこれは天賦の才とも違うし努力の産物とも別の、そういうものが全部一緒になった何かの作用によるものなのだと思える。しかも、私は今なお、岡崎律子と日向めぐみのどちらがどの曲を書いたのか、よくわかっていない。だからこのことは岡崎か日向のいずれかの話ではなくて、まさにメロキュアというユニット自体に言えることなのだ。メロキュアというネーミングは、メロディとキュアの合体だろうが、二人はどこを取っても完璧にしっくりくる文句なしの旋律性によって、大袈裟にいうなら「ゼロ年代以降のニッポンの音楽」自体を治療してみせている。
オリジナルのアルバムがリリースされてから十年余、メロキュアのメロディはかけらも古くなっていない。今回の「復活」によって、私のように、こちら方面に疎いがゆえにこれまでメロキュアの存在を知らなかった音楽好きが、彼女たちと出会うことになるといいなと思う。
■佐々木敦
批評家。音楽レーベルHEADZ主宰。早稲田大学文学学術院教授。
著書に『ニッポンの音楽』『あなたは今、この文章を読んでいる。』『「4分33秒」論』など。