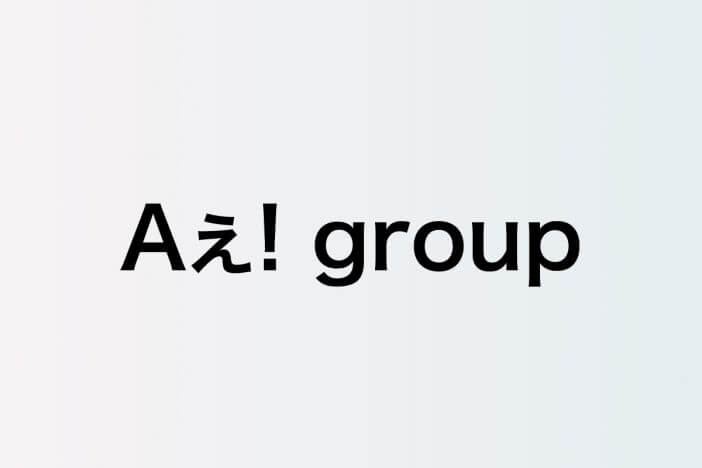3rdアルバム『Blue Avenue』レビュー
花澤香菜は第2の松田聖子となるか? 栗原裕一郎が新作の背景と可能性を探る
ジャズ、フュージョン、AORとしてのニューヨーク
「ニューヨーク」といわれてどんな音楽をイメージするかは人それぞれだろうが、このアルバムが想定しているのは、80年前後のフュージョン、AORなど、あの時代に鳴っていたあの音だ。
ジャズ的な要素も、当時のジャズそのものというより、M7「Night And Day」、M12「マジカル・ファンタジー・ツアー」のビッグバンド・アレンジに顕著だけれど、1920年代ジャズエイジのリバイバルとしてあの頃に流れていた音楽である。M1の参照元である「A Night in New York」もそうだし、1920年代ハーレムのナイトクラブを華麗に描いたコッポラの映画『コットンクラブ』が大ヒットしたのは84年のことだ。M9「タップダンスの音が聴こえてきたら」のモチーフもこの流れから出てきている。
レファレンス先の痕跡を残しているのは、アルバムのコンセプトを明確にするための意図的な選択だろうし、詳しい人が聴けば、それこそ渋谷系のような元ネタ探しを楽しむこともできるだろう。
ミト作編曲のM5「Trace」はスティング「Shape of My Heart」を意識したものであることをイントロのギターアルペジオで宣言しているし、矢野博康によるM9「We Are So in Love」は、ギターがもうこれぞ80年代フュージョンという音色とフレージングで変な汗が出てきそうだ。ラストを締め括る NONA REEVESの西寺&奥田によるM14「Blue Avenueを探して」は“ドナルド・フェイゲン歌謡”である。奥田が『リスアニ!』のアンケートでそういっているのだ。「Walk Between The Raindrops」のシャッフルのイメージか。
しかし、ジャズエイジ・リバイバルのさらなる再解釈を基調としたニューヨークというのもかなり入り組んだ話で、聴いていてなんとなく、ダフト・パンクがEDMブームに反旗を翻してディスコに回帰してみせた『Random Access Memories』を連想したりもした。
高解像度のシミュレーションにより単なる懐古趣味に留まらない今日性を得ている点も共通しているが、決定的なのは声だ。ダフト・パンクがロボ声によって現在を告げているように、『Blue Avenue』は、花澤香菜の声によって、これらが2015年の音楽であることを告げているのである。