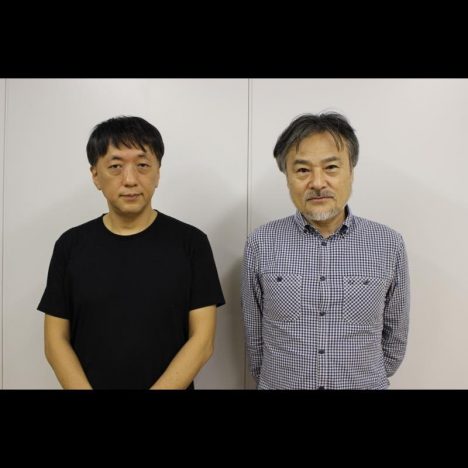宮台真司の月刊映画時評 特別編
宮台真司×黒沢清監督『スパイの妻』対談:<閉ざされ>から<開かれ>へと向かう“黒沢流”の反復

リアルサウンド映画部にて連載中の社会学者・宮台真司による映画批評「宮台真司の月刊映画時評」。今回は特別編として、10月16日に最新作『スパイの妻』が公開となった黒沢清監督との対談を掲載する。以前から黒沢監督の手腕を高く評価してきた宮台が、『スパイの妻』を起点に、黒沢監督ならではのモチーフの反復、フィルムというモノに対するフェティシズム、本作が無意識下で伝えている現代社会への痛烈なメッセージに迫る。
“黒沢流”のモチーフの反復が意味するもの

宮台真司(以下、宮台):最初に少し個人的な話をすると、僕の母方の祖父は、フランス租界にあった上海自然科学研究所の教授だったので、母の家族は租界地で暮らしていたんです。今作『スパイの妻』の優作とその妻・聡子と同じように、お手伝いが5人いるという環境で、想像を絶する大豪邸に住んでいました。母によると、母の両親であるその教授と妻ーーつまり僕の祖父母ーーは「とにかく早く日本が戦争に負ければいい」とずっと言っていたそうなんです。そういったこともあるので、「全く他人事として観ることができない」という、黒沢作品を観る僕としては非常に珍しい体験になりました。
『スパイの妻』は、黒沢監督独自の物語の構造と画面構成がきっちりと維持・反復されていながら、誰にでもわかる娯楽性とメッセージが満ちているという意味で、「黒沢映画入門編」であると同時に、そのメッセージ性がすごく社会的に評価されるべきものに昇格していると思いました。これが、拝見しての第一印象です。
先ほど述べたように、黒沢流のモチーフの反復があります。それは微睡(まどろみ)/覚醒、正景(まともな風景)/廃墟、そして狂気/正気です。まず、今回の映画で微睡んでいるのは、妻です。彼女は、満州に出かけてストレンジャーStrangerに変じた夫の、不可解な行動を通じて、最終的に覚醒。夫と同じように、妻もまた、この現実が既に廃墟であることーー徹底的に終わっていることーーを知ります。そこからの救済Salvationの道も、これまた従来の黒沢作品と同じく、「自らも狂人になる」という選択でした。
しかし、今回の作品は「そもそも言葉と法と損得によって営まれる<社会>は、例外なく廃墟なんだぞ」という高度な抽象水準の黒沢作品群とは違い、特定の<社会>の在り方を標的にしています。戦時の<社会>でも現代の<社会>でも構わないのですが、<社会>において「まともであることで狂人扱いされる」時代がしばしばあり、「そうした<社会>においては、あえて狂人であり続けることこそが、まともさの証だ」というメッセージが与えられるのです。「抽象度が違えど、これぞ黒沢流だ」と、本当に感心しました。
劇の後半でも、セリフとしてそのことが明確に示されます。そもそも冒頭、壁・窓・扉を背景にして人が集まる、ヨコ構図の深度のないシーンが、もうゾクゾクするのです。今回の黒沢流においては、これは人が微睡の中で狂気に陥っているぞと告げるオラクル(お告げ)になっています。まず最初に、世界観から、画面の細部にまで至る、こうした「黒沢流」を、どのように意識し、活かそうと思われたかをお伺いしたいと思います。

黒沢清監督(以下、黒沢):まず、大変に細かい点まで観ていただいた上に、予想もしないような嬉しいお言葉までいただき、ありがとうございます。大変恐縮しているのですが、「黒沢流」というものをそれまで強く意識したつもりはないのです。
宮台:黒沢監督は、いつもそう仰います(笑)。
黒沢:ただこれまでの作品は、東京近郊である不可解なことが起こり、人が右往左往するドラマをどう撮るかという考えから編み出されたものですが、今回は初めて歴史的モチーフを扱っているわけです。だから、東京の適当な場所でカメラを回すことは許されない現場だった。これまでは多くの素材がある中でどこを切り取るか考えていたわけですが、今回はある特定の歴史の枠内に様々な人やモチーフを押し込めて、作らなければならなかったんです。このような発想で作ったことは初めてでした。ただ、作品が出来上がってラッシュを観たり、編集したりしているうちに、この2つの発想は、そう違わないものかもしれないと思いはしたのですが。
廃墟というモチーフに関しては、今回は扱うのが少し大変でした。というのも、劇中の時代当時の面影を残している場所はもうすでに廃墟のような場所であったり、もしくはピカピカに修復された上で保存されている。後者は法的に映画撮影ができないことも多かったので、すでに廃墟となっている場所を使用することになる。そうした際にどのように、一方は本当の廃墟として、もう一方は劇中において賑わっているように見せるか苦心しました。その点はこれまでとはだいぶ違っていました。