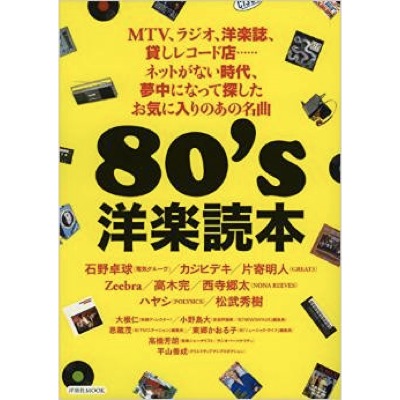『ジョン・ライドン 新自伝 怒りはエナジー』出版記念対談
日高央×小野島大が語る、ジョン・ライドンの比類なき音楽人生「ジョニーは革命を2回起こした!」


ジョン・ライドンがロバート・プラントみたいなヴォーカリストだったら…(小野島)
――ジョン・ライドンは1956年生まれで、今年で還暦ですね。
日高:意外と若いですよね。
小野島:まったく同い年なんですよ(日本流に言えばジョンが一学年上)。
日高:そうなんですね。ジョン・ライドンも予想以上にいろんな音楽を聴いてきたみたいですけど、共感する部分もありますか?
小野島:一概に共通体験としては語れないだろうけれど、僕がいきなり最初からパンクを聴いていたわけではないのと同様、彼も最初からパンクだったわけではない。それなりの経緯をたどって、こういうことをやりだしたんだろうな、というのは分かりますね。
――自伝を読むと、ジョン・ライドンはデヴィッド・ボウイやT・レックスをかなり高く評価していますね。
日高 そうですね。グラムロックは好きでしたね。
――ただ一方で、ニューヨークパンクに対しては辛辣で。
日高:マルコムのせいもあるのかもしれないですね。
小野島:ラモーンズなんかも完全に否定していて。あれはなんだったんでしょうね。
日高:マルコムのマブダチだからとか、それくらい単純な理由な気がします(笑)。
小野島:あ、ラモーンズにインタビューした時、「俺がパンクを作ったんだ」ということをわりと堂々と言っていたけど、ジョンはそういうことは言わないですね。それも気に入らないのかも。
日高:大勝軒の本家争いみたいな(笑)。
――それにしても、なぜここまでマルコムを嫌うのか。
小野島:本当にボロカスに書いていますからね。前の自伝(『STILL A PUNK』)ではそうでもなかったのに。
日高:そうですね。ピストルズの終わり方って、ツアーのビデオを観ていても辛いじゃないですか。もう悲しみしかなくて、もしかしたらジョンの中でのパンクロックって、あの時のままなのかな、というのはすごく思います。PiLは全然違うものになっているじゃないですか。俺は演者の立場だから、これがよく分かるんです。正直、「もうビークル(BEAT CRUSADERS)みたいなものは期待しないで」と思うんですよね。だけど、リスナーからすればいまだに“ビークルの日高央”という部分もあるだろうし。ジョンなんて、俺の何百倍、何千倍も言われるわけじゃないですか。「お前はジョン・ライドンじゃなくて、ジョニーロットンだろ!」って四六時中言われて、その憂さを全部マルコムのせいにしているんだとしたら、なるほどと思うんです。
小野島:なるほど。でも本を読むと、話の成り行きによってはピストルズを続けてもよかったというか、「続けたかった」という感じもするんですよね。でもマルコムが嫌いとか、他のメンバーがやる気がないとか、いろいろな事情が重なって結局やめざるを得なくなったという。
日高:それも演者目線で見ると、たぶん、ジョンはメンバーのことが好きなんですよね。特にシドのことは好きじゃないですか。ポール・クックとかスティーブ・ジョーンズに対しては分からないし、(初代ベースの)グレン・マトロックのことはボロクソに言ってますけど(笑)。ただ、やっぱりメンバーとマネージャーは全然別もので、純粋にバンドキッズとして、「ただただ、あいつらと一緒に音楽をやりたい」というのは、演者としてすごく分かる。バンドが終わっていくのもよく分かって、例えばビークルも売れすぎたんですよね。ビークルって、もともと嫌がらせじゃないですか。紙のお面で顔も見せずに、ライブでは卑猥なことを言って。でも、売れるとそれが褒められちゃう。女の人が“私もオマンコールしてます!”みたいなことを言っちゃったり(笑)。いや、それは怒ってほしくてやっているのに、という。それが通じなくなって、結局終わっちゃうんですけどね。これはメンバーが悪いとか、お客さんが悪いとか、そういうことじゃない。俺が同列に語るのもおこがましいですけど、読んでいてそういうことは思いましたね。バンドマンなら読んだほうがいいかもしれない。
――バンド活動にまつわる教訓も含んでいると。
日高:もちろん、ジョンほどひねくれる必要はないんですけど、スタッフやメンバーに対するモノの見方や考え方の極端な例として(笑)。ミスチルからズブの素人バンドまで、バンドマンなら誰でも楽しく読める気がします。

小野島:ピストルズが再結成したのは、お金というのもあるのかもしれないけど。観客が恋しくなったということもあるんですかね?
日高:そうですね。PiLがあまりうまくいってないというのも、あったのかもしれない。あと、ジョンってけっこう男気の人じゃないですか。だから、メンバーの誰かを助けよう、という思いもあったんじゃないか、と。スティーブ・ジョーンズなんかは要領が良いけれど、ポール・クックなんか確実にしょぼくれているから。あるいは、シドの遺族に対して何かしたいとか。
小野島:それはけっこうある気がする。ザ・フーの再結成だって、(ベーシストの)ジョン・エントウィッスルが生活に困窮して、彼を助けるためにやったみたいな話もあるし。ただ本を読んでいると、ジョンは再結成について斜に構えた感じでもなく、最高の瞬間を待っていたぜ、みたいな感じで書いていますけどね。
日高:バンドのスゴさって、本人はあとから実感するんでしょうね。俺にとってのビークルも、ただただ自分が作ったもので、キレイなものでも汚いものでもあるし、もうよく分からない。それがピストルズというレベルになると、世界中を巻き込んでのカオスになっちゃってるから。だから、ピストルズは意外と悪くなかったなと、年々しみじみ思ってるんじゃないないかなって。
小野島:武道館公演を観に行ったら、「なんだ、普通にうまいじゃん」って思うんですよ(笑)。我々でさえ、なんとなくゴチャゴチャのカオスな演奏を期待していたところがあったので、わりとちゃんとしていて。アレンジは昔のままなのに。
日高:よくできているんですよね、ピストルズって。別に難しいことはやっていないけれど、正直、ラモーンズよりちゃんとアレンジされているというか。アメリカのバンドに比べてすごくタイトに演奏していくというか、ガレージ感があまりないので、日本人の肌にも合いますよね。まあ、ジョンは人としてはガレージ感がハンパないですけど(笑)。
――アメリカに移住して30年だそうです。
日高:意外ですよね。アメリカのこと嫌いそうだけど、イギリスのほうが嫌いなのかな。
小野島:ロンドンで散々な目に遭った、みたいな話は聞きますね。あと、奥さんが新聞王の娘で、全然あくせくしないでいい、みたいな。10いくつ年上なんだけど、奥さん一筋なんですよ。この本を読んで思ったのは、“セックス・ドラッグ・ロックンロール”というけど、この人は女遊びに執着はなさそうだし、ドラッグもやっていたけれど耽溺性はないということだし……。
日高:ロックンロール一筋ですね。
小野島:そう、意外とストイックというか。シドもナンシー・スパンゲンが初めての女性で、死ぬまで一緒だったって言うし。
日高:ああ、ピストルズって相当純粋にバンドバンドしてたのかもしれないですね。パンクっぽい主義主張が置き去りにされて、現代の耳だけで聴いてカッコわるく言われちゃうこともあるのが皮肉な話で。ヘタしたら、音楽そのものに加えて、言いたいことがあるかないかのほうが重要視されるのがパンクの本来の良さだというのに。たぶん、小野島さんの世代でかなり議論されたところだと思うんですけど。例えば、メタルとパンクって、仲が悪かったじゃないですか。
小野島:ありましたよね、対立事項がね。でも、ピストルズはやっぱり、新しいハードロックとして聴いていた部分がありましたよ。レッド・ツェッペリンとかディープ・パープルを聴いていた子どもからすると、一番カッコよくてスカッとするハードロックで、ダラダラとしてギターソロはやらないけれど、ほんの数小節のスティーブ・ジョーンズのソロがカッコいい、とか。
日高:でも、面白いですよね。この間、ラジオでパワーポップについて話していたんですけど、みんながプログレをやっているときに、もう一度ビートルズっぽいことをやろうというのがパワーポップだったじゃないですか。その意味で、ジョン・ライドンってビートルズが好きなわけじゃないのに、割とパワーポップに発想が近いというか。みんなが長尺の曲を作って、スタジアムでライブをして、というなかで、もっとコンパクトなものを志向していて。もし、ジョン・ライドンがちゃんと歌えていたら歴史は変わったのかな、とも思うんですよ。この歌い方だったからよかったんだし、逆にちゃんと歌えていたら、パンクになっていなかったのかもと思うというか。
小野島:ジョン・ライドンがロバート・プラント(レッド・ツェッペリン)みたいなヴォーカリストだったら、ピストルズは3流のハード・ロックで終わったんでは?(笑) でも、ボーカルスタイルがその人の音楽性を決めるという話は昔からよくしていて。例えば、小室哲哉さんなんかも、「小田和正みたいなボーカリストだったら、プロデューサーをやっていましたか?」と聞いたら、「絶対やっていないです」と言い切っていましたよ(笑)。
日高:なるほど、それは面白いですね。俺も本当は渋谷系みたいなオシャレなことをやりたかったんですけど、声がガサガサだからできなくて。それでラウドの方に進んだら、なんとなくそこにハマったんですよね。
小野島:(笑)田島貴男みたいなボーカリストだったら違ったと。
日高:そうですね(笑)。いずれにしても、ジョン・ライドンの魅力って、やっぱりまずは歌声なんですよね。本人が一番それを分かっていないし、たぶん認めたくない、恥ずかしいところだと思うんですけど。
小野島:ボーカリストとしてコンプレックスはあるのかね、この人は。
日高:100人いれば全員、あると思いますよ。レコーディングをしていればなれますけど、やっぱりラフとかで自分の歌だけが流されると、本当に死にたくなる(笑)。ちゃんとミックスされて、やっと客観的に聴けるというか。